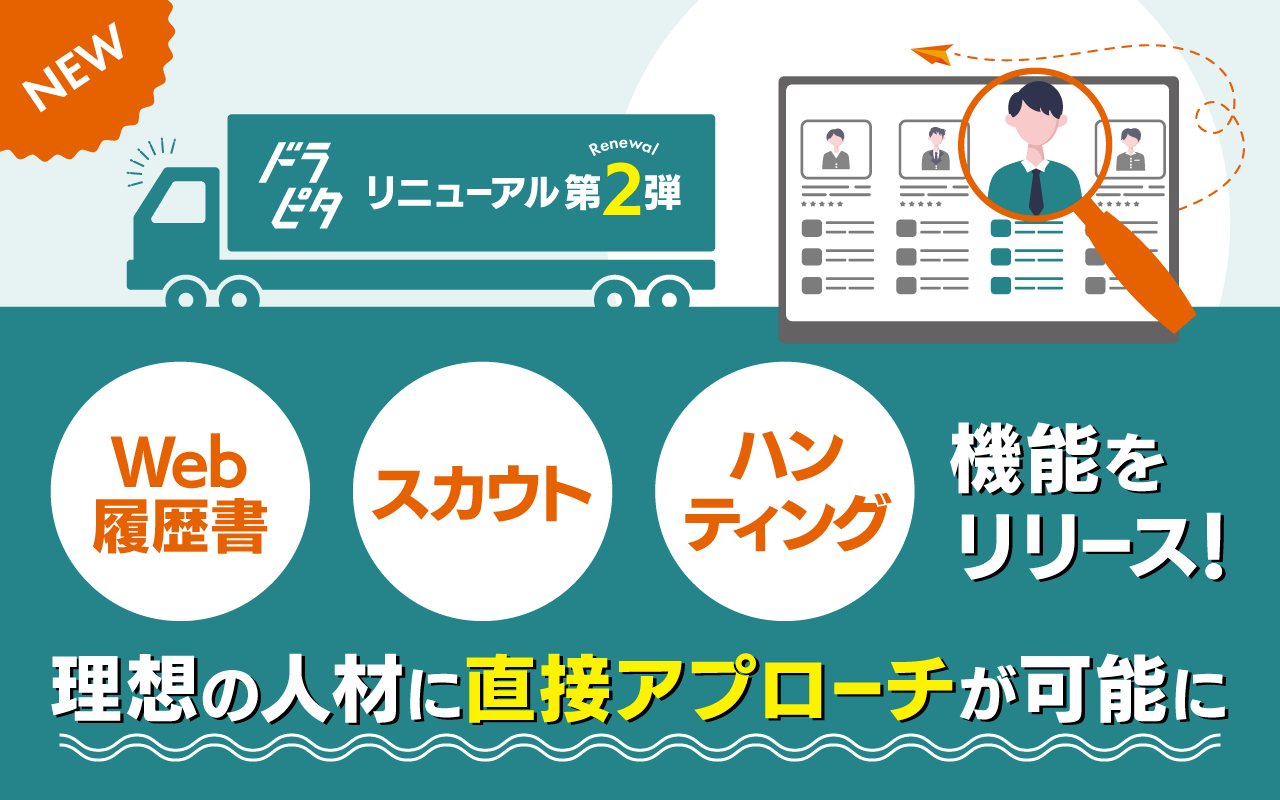近年、物流・運送業界のドライバー不足が深刻化しており、頭を悩ませている企業もいるでしょう。
ドライバー不足への対策は、自社の労働環境や運営方法を見直すことが大切です。
この記事では、ドライバー不足対策としておすすめの解決方法や原因、企業の取り組み事例をご紹介します。
また、効果的なドライバー募集についても解説しますので、自社の人手不足にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
ドライバー不足対策|おすすめの解決策

この章では、ドライバー不足への対策をご紹介します。
おすすめの解決策8選は下記のとおりです。
- 労働環境の見直し
- 予約受付システムの導入で荷待ちの時間を削減
- ドライバー未経験者の教育体制を整備
- 荷役作業を機械化
- 拠点を分散させる
- モーダルシフトの導入
- 共同配送の導入
- 応募する人の目線に合わせた広報活動
それぞれの解決策について詳しく見ていきましょう。
労働環境の見直し
運送業では、長時間労働の慢性化や低賃金がマイナスなイメージを持たれやすく、それらのイメージを払拭していく必要があります。
イメージの改善には、下記のような労働環境の見直しが必要です。
- 労働時間を短くする取り組み
- 休暇を取得しやすい環境を整備
- 労働時間に見合った報酬水準の引き上げ
ドライバーが働きやすい環境を整えるには、長時間労働の抑制や休暇の取りやすい環境に加えて、働きに見合った給与水準を見直していく必要があるでしょう。
予約受付システムの導入で荷待ちの時間を削減
荷待ちの時間は、ドライバーの長時間労働の原因の1つです。
ドライバーの負担になるだけでなく、待機する物流倉庫で働く作業員への負担や、荷待ちトラックが増えることで近隣住民にも負担となる可能性があります。
荷待ち時間問題は、予約受付システムの導入で、トラックの到着時間の分散ができるようになり、トラックドライバーの長時間待機を削減できます。
物流倉庫でも計画的に荷物を準備できるため、輸送効率の向上にも繋がるでしょう。
ドライバー未経験者の教育体制を整備
ドライバー未経験者の教育体制を整備することで、初心者でもスムーズな採用が視野に入れられるようになります。
また、初心者ドライバーが分からないことや疑問・不安に対応できるようになることで、離職率の低下も期待できるでしょう。
荷役作業を機械化
さらなる運送の増加が見込まれる昨今、現状の限られた人数で、増加傾向にある物流量に対応するためには、作業の機械化や自動化が欠かせなくなってきています。
具体的には、物流倉庫での荷役作業を機械化することで、ドライバーの負担を大幅に軽減できます。
拠点を分散させる
拠点を分散させることで、各拠点同士の距離や時間が短くなるため、配送効率を上げられる可能性が高まります。
全体の輸送コストの削減も期待できるでしょう。
拠点を分散させておけば、災害時でも被災地以外の物流を止めずに済む可能性もあります。
ただし、拠点の運営維持費や振り分け作業など、コストの増加と処理が煩雑になる可能性がある点に注意が必要です。
モーダルシフトの導入
モーダルシフトとは、トラックによる陸上輸送の代わりとして、鉄道や船舶を活用した輸送方式のことです。
トラックによる長距離輸送が削減できるため、ドライバーの長時間労働が解消できるメリットがあります。
また、トラックによる輸送に比べて、環境負荷が少ないことも魅力の1つです。
国土交通省の「モーダルシフト等推進事業」では、500万円を上限に導入支援も行っているので、制度を活用した導入もできるでしょう。
ただし、配送のリードタイムが延びる可能性がある点に注意が必要です。
共同配送の導入
共同配送とは、複数の運送事業者が協力して、同一の納品先へ荷物を運ぶ方式のことを指しています。
共同配送の拠点に荷物を集めるため、納品先へ向かうトラックとドライバーの数を削減できるメリットがあります。
ただし、共同配送を行う事業者同士の情報共有や、調整が必要となるため、新たな業務が増える可能性がある点を考慮しなければなりません。
応募する人の目線に合わせた広報活動
ドライバーの募集をする際は、働き手の目線に合わせた内容で活動することがおすすめです。
例えば、資格や役職に対してどのような優遇制度があるのかを紹介したり、実際に働くドライバーを紹介したりするなど、就職後の勤務状況がイメージしやすいようにするとよいでしょう。
また、インターネットやSNS等を活用した広報活動も効果的です。
ドライバー不足は嘘?噂される理由を解説
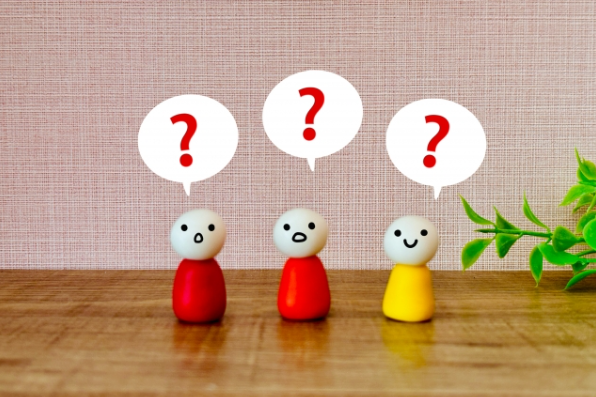
ドライバー不足が、深刻化しているとの情報を聞いた方のなかには「ドライバー不足は嘘なのでは?」と疑問に感じる方もいるようです。
上述で紹介したように、ドライバーの不足が深刻化しているのは確かな情報といえます。
ただし、適切な採用戦略と求人内容の工夫によって、良質な応募者を確保できるケースもあり「ドライバー不足」と言い切れない状況もあるのが事実です。
実際に、効果的な採用戦略を実践することで、良質な応募者を確保している企業も存在しています。
適切な戦略をもって募集をかけている企業には、多数の応募者がいるため、ドライバー不足は嘘だと感じる場合もあるでしょう。
例えば、応募者を増やすには、下記の点に留意した採用戦略が必要です。
- 求人広告を出す場所を選ぶだけではなく、その広告の内容や応募者にアプローチする方法が重要
- 自社の魅力を伝える際には、求職者が何を求めているのかを深く理解し、それに応える内容を提供
- 応募が期待通りに集まらない場合は、その理由を深堀りしPDCAを回すことが重要
少子高齢化が進み、全職種において人手不足は深刻化しています。
そのなかでも応募者が多い企業は、人材募集において的確な戦略をたてているのです。
効果的なドライバー募集の掲載なら、全国に対応している求人・転職サービスの「ドラピタ」に掲載がおすすめです。
「ドラピタ」では、ドライバー案件に特化した職種軸で検索が可能なため、貴社の狙ったターゲットへ求人原稿を訴求できます。
掲載について詳しく知りたい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
ドライバー不足解消に向けた取り組み事例12選

この章では、実際にドライバー不足解消に向けた取り組み事例をご紹介します。
各企業の主な取り組みは、下記の表を参考にしてください。
|
企業名 |
取り組み |
|
ジャスト・カーゴ |
退職金の整備や無事故運転を続けることにより、給料のベースアップを行っている |
|
石原運輸 |
・長時間労働を防ぐため1 泊の運行は極力断るようにしている ・勤務時間や仕事内容は多様な働き方に対応している ・整備士を雇用し、ドライバーへの負担を軽減している ・荷積み・荷卸し作業をお客様で対応してもらっている |
|
丸山運送 |
・入社時に免許保有の有無による制限はなく、ステップアップ制度を利用してペーパードライバーからドライバーも可としている ・女性ドライバーには地場便を担当してもらっており、その日に帰宅できるようにしているほか、体力面を考慮し、省力化を図るようにしている |
|
TAKAIDO クールフロー |
・3ヶ月に1回、社内報を発行し、全社員へ理念・経営方針を伝えるとともに、自宅に送ることで家族にも見てもらえるようにしている ・働き方改革プロジェクトチームを設置して、管理職に現場を把握している社員を加えた人員で構成している ・現場の声を把握するために、全社員を対象とした意識調査を実施している ・長期無事故無違反者や永年勤続者などに表彰式を行っている |
|
NTS ロジ |
・出勤態度ややる気を評価する評価制度を導入している ・不満等、管理職に言いづらいことも、できるだけ次の日に切り替えができるように終業点呼は女性が対応するようにしている |
|
寒川運送 |
・他社よりも給料を高く、休みを多く、働く時間を短くするように努力している ・5年勤続することが前提ですが、免許取得費用を負担している ・無事故による手当の支給を行っている |
|
ツカサ |
・労働条件改善に取り組み(パレット積みに変更、1台で回る運送ダイヤの変更) ・高齢ドライバーも働けるように定年の引き上げを行った |
|
アトランス |
・健康診断を含めた健康管理の強化・健康という切り口で社員との信頼関係を築いている ・高齢者にはフォークリフトを使った荷役やパワーゲートリフター付車両、時短勤務等、個々に応じた形態としている |
|
つばめ急便 |
・乗務員を事故やトラブルから守るために、衝突被害軽減ブレーキシステム、デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーバックカメラ等の安全機器装備車両を配置している |
|
KUBOXT |
・本人の努力を給与に反映させるため、車種ごとに等級制を導入している ・60 歳の定年後でも働きたい方には続けてもらい、同じ仕事をする場合は同じ給料を支払っている |
|
大輪総合運輸 |
・経営と従業員との考え方のギャップを縮めるために、個別ミーティングの頻度を増やしている ・金銭や保証といった外的報酬の他に、承認欲求や成長欲求を満たす内的報酬を高めることを重視している |
|
肥前通運 |
・契約社員1年→準社員1年の通常2年を目途に正社員に昇格できるシステムではあるが、特に優秀な方については最短1年で正社員化としている ・大型免許取得支援制度規定も新設している ・健康管理講習会を開催している |
参考:国土交通省「ドラックドライバーの採用・定着に向けた取組事例・ポイントを紹介します」
上記の事例では、新規採用者に向けた免許取得の支援、女性や高齢者の働きやすさを重視した労働環境整備、就労の定着のための収入アップ制度などが多い印象です。
運送・物流業界のけるドライバー不足の現状と今後の予測

この章では、運送・物流業界におけるドライバー不足の現状と今後の予測について解説します。
トラック運転者の有効求人倍率
厚生労働省の一般職業紹介状況(2024年9月分)によると、トラック運転者の有効求人倍率は2.62倍、全職種計の1.14倍と比べると2倍以上高いことが分かります。
上記の結果でも、ドライバーの需要が供給に対して大きく上回っており、人手不足が深刻化していることが理解できるでしょう。
今後のドライバー不足の予測
2012年から現在まで、ドライバーの従事者は約84万人と横ばいで推移していますが、インターネット上で簡単に買い物ができるようになり、個人宅へ配送する荷物数も増加していることで、ドライバー不足が加速しているのが現状です。
また、公益社団法人鉄道貨物協会国土交通省「平成30年度本部委員会報告書」では、2028年度には約27.8万人のドライバー不足が予測されており、今後もドライバー不足は進行する可能性が高いといえるでしょう。
なぜドライバー不足が深刻化しているのか

この章では、ドライバー不足がなぜここまで深刻化しているのかについて解説します。
主に下記の理由が原因として挙げられます。
- 宅配の需要が増加し続けている
- 労働条件と賃金が見合わない
- ドライバーの高齢化が進んでいる
- 女性ドライバーの数が少ない
- 運転免許制度の改正で免許の取得が必要になった
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
宅配の需要が増加し続けている
EC市場の成長やフリマアプリなど、個人間取引の増加により、近年、宅配の需要が急速に増加しています。
宅配需要に対してドライバーの数が追いついておらず、実質的なドライバー不足が生じているのが原因です。
また、配送個数が増えるだけでなく、時間指定や当日配送、再配達などのサービスの多様化から、物流業界全体に大きな負担がかかっているのもドライバー不足に拍車をかけていると考えられます。
労働条件と賃金が見合わない
物流・運送業界のドライバーは、他の職種に比べて収入が低く、労働時間が長い傾向にあります。
そのため、長時間労働と低賃金のイメージが定着し、新たにドライバーを確保するのが難しい状況にあるといえるでしょう。
2024年4月の法改正によって、ドライバーの労働時間の上限規制が設けられ、長時間労働の改善が期待されていますが、ドライバーにとって労働時間の減少は収入減につながるため、懸念の声も上がっているのが現状です。
ドライバー不足解消のためには、労働環境の改善だけではなく、長時間労働と低賃金の両方の課題解消が必要となるでしょう。
ドライバーの高齢化が進んでいる
厚生労働省「統計からみる運転者の仕事」によると、全産業とトラック運転者の平均年齢を比べた結果、トラック運転手の年齢が比較的高い傾向にあることが分かっています。
具体的な平均年齢は下記のとおりです。
- 大型トラックの平均年齢:49.9歳
- 中小型トラックの平均年齢:47.4歳
- 全産業平均:43.4歳
今後、退職者の増加も予測されるため、ドライバーの高齢化がドライバー不足を加速させる原因の1つになる可能性が高まっています。
女性ドライバーの数が少ない
全産業と比べると、ドライバーを職種に選ぶ女性が少ないことも原因の1つといえます。
育児休業や再雇用制度の整備など、女性が働ける環境が整っていないことも、女性ドライバーの進出が遅れている要因といえるでしょう。
また、長時間労働だけでなく、力仕事や体力面で女性が働ける業務が限定されるのも原因の1つです。
運転免許制度の改正で免許の取得が必要になった
平成29年に改正された運転免許制度によって、準中型免許が新設され、それまで普通免許で運転可能だった2トントラックが運転できなくなりました。
法改正により、ドライバーとして働くためには、運転免許を新たに取得しなければならないケースも出てきましたが、準中型免許を取得するための費用負担が大きく、新規参入の妨げになっているのも原因といえるでしょう。
ドライバー不足は求人内容の工夫で対策していこう
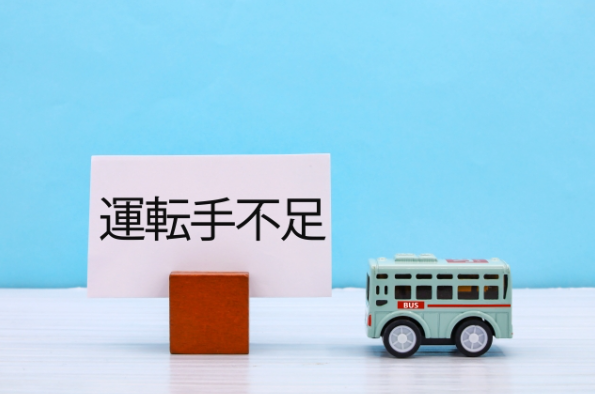
物流・運送業界のドライバー不足は、年々深刻化しています。
ECサイトを含む個人間の取引が増加しているため、今後はさらなる人手不足になることが推測されます。
ドライバー不足の対策としては、労働環境の改善や、システムの導入など、入社後の労働負担を軽減していく必要があるでしょう。
ドライバー不足は適切な採用戦略と求人内容の工夫によって、優秀な応募者を確保できる可能性が高まります。
もし、トラックドライバー探しにお悩みなら、全国に対応している求人・転職サービスの「ドラピタ」に掲載がおすすめです。
「ドラピタ」では、ドライバー案件に特化した職種軸で検索が可能なため、貴社の狙ったターゲットへ求人原稿を訴求できます。
掲載について詳しく知りたい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。