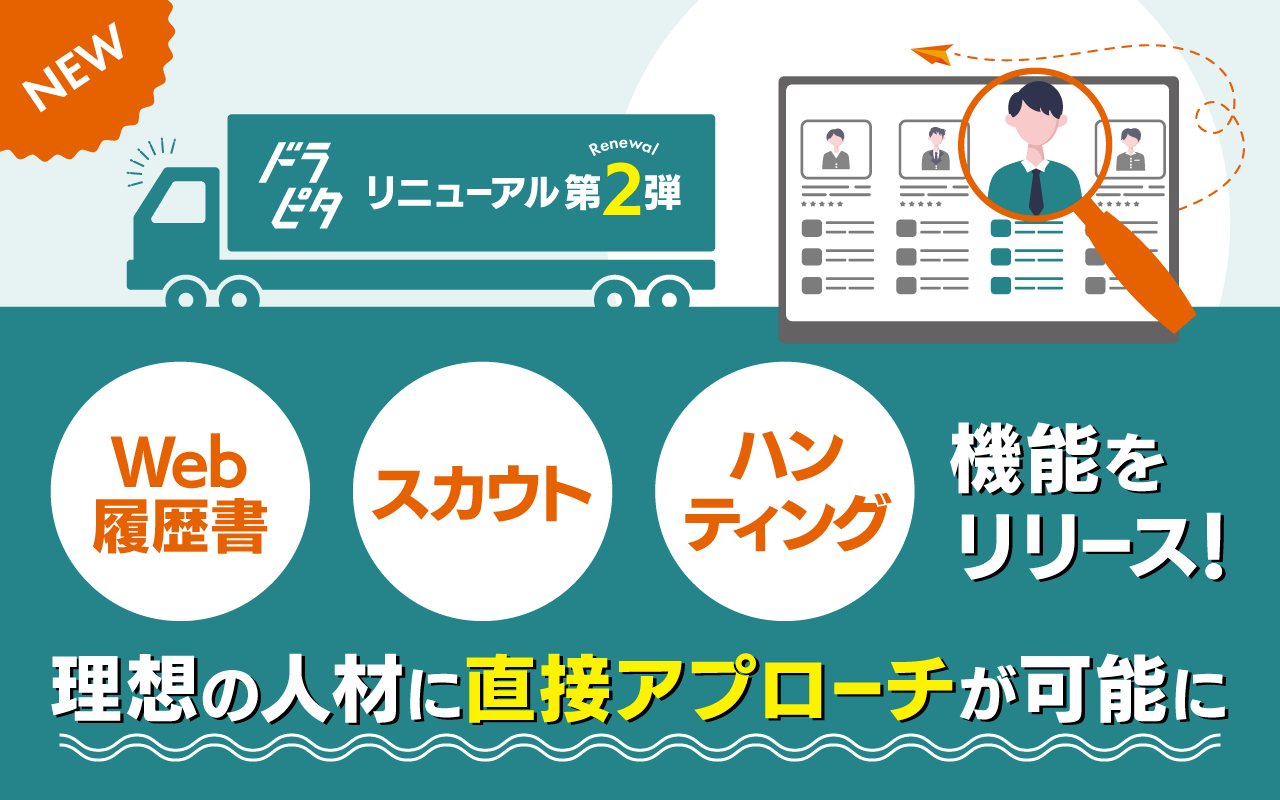Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)の有無を、取引先の荷主から確認されたことがある事業所もいるでしょう。
Gマーク認定を受けることで、どのようなメリットが得られるのか詳しく知りたい方も少なくありません。Gマーク認定は、ほかの事業所と差別化を図るのにも効果的です。
この記事では、Gマーク認定を受けるメリット・デメリットを詳しくご紹介し、申請資格や条件・流れについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
Gマーク認定によるメリット一覧

Gマーク認定で得られるメリットは、大きく分けると4つあります。詳細な内容を下記の表にまとめました。
| メリット | 詳細 |
| 安全性向上によるメリット | 【1】事故発生の頻度を抑えられる
【2】荷主からの信頼度が高まる 【3】経費削減につながる |
| 国土交通省から得られるメリット | 【1】行政処分による違反点数が2年間で消去される
【2】IT点呼の導入が可能になる 【3】点呼が優遇される 【4】安全性優良事業所として表彰される 【5】基準緩和自動車の有効期間の延長 【6】特殊車両通行許可の有効期間の延長 |
| 日本トラック協会から得られるメリット | 【1】ドライバー等安全教育訓練促進助成制度の優遇
【2】安全装置等導入促進助成事業の優遇 【3】経営診断受診促進助成事業の優遇 【4】自動点呼機器導入促進助成事業の優遇 |
| 損保会社から得られるメリット | 一部の保険会社の保険料割引 |
次の章から、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
安全性向上による3つのメリット

Gマーク認定によって、自社の安全性が向上します。安全性向上による具体的なメリットは下記の3つです。
- 事故発生の頻度を抑えられる
- 荷主からの信頼度が高まる
- 経費削減につながる
上記のメリットを詳しく見ていきましょう。
【1】事故発生の頻度を抑えられる
Gマーク認定のために、安全性の向上に向けた取り組みが必要になります。これらの取り組みにより、運送事業者だけでなくドライバーも安全への意識が高まるため、事故減少につながるメリットが得られます。
【2】荷主からの信頼度が高まる
Gマーク認定事業所は、優良なトラック運送事業者として、荷主からの信頼を得ることができます。
「経団連の安全運送に関する荷主としての行動指針」にも、Gマーク認定企業を活用するように記されているため、Gマーク認定により、荷主企業に選ばれやすい会社となるでしょう。
【3】経費削減につながる
安全性向上の取り組みによって事故が減少すれば、自動車保険や貨物保険などの保険料も減少していきます。結果として、経費の削減につながるでしょう。
さらに、Gマーク認定項目の1つであるグリーン経営認証、ISO14000シリーズ、エコシリーズ認証、エコアクション21などの認定を受けると、燃料費や車の修繕などの経費を削減することにつながります。
国土交通省から得られる6つのメリット

Gマーク認定を受けた事業者に対して、国土交通省は、下記のインセンティブを実施しています。
- 行政処分による違反点数が2年間で消去される
- IT点呼の導入が可能になる
- 点呼が優遇される
- 安全性優良事業所として表彰される
- 基準緩和自動車の有効期間の延長
- 特殊車両通行許可の有効期間の延長
上記のメリットは、運送会社の運営に大きなメリットとなるため、詳しく見ていきましょう。
【1】行政処分による違反点数が2年間で消去される
Gマーク認定を受けている事業所が、行政処分を受けた場合、違反点数が付与される期間が短くなるメリットが得られます。
通常の違反点数付与期間は3年となっていますが、違反点数が付与されてから2年間、違反がなかった場合、違反点数が消去されます。
運送会社で科される可能性がある行政処分は、下記のとおりです。
- 車両使用停止:一定期間トラックの使用ができなくなる
- 事業停止:一定期間運送業を行うことができなくなる
- 許可取消:運送業許可が剥奪される
また、行政処分による違反点数の累積が過去3年間で20点を超えてしまうと、Gマーク認定が取り消されてしまうので、注意しましょう。
【2】IT点呼の導入が可能になる
Gマーク認定を受けた事業所は、IT点呼の導入が可能になります。国土交通大臣が定める設置型か、携帯型カメラ付きの機器による点呼が認められます。
Gマーク認定がある事業所では、事業所間、事業所車庫間、事業所遠隔地でIT点呼ができるようになり、具体的なIT点呼の可能範囲は下記のとおりです。
- A営業所~A営業所の車庫
- A営業所の車庫~A営業所の他の車庫
- A営業所~B営業所
- A営業所~B営業所の車庫
離れた場所で点呼が可能になるため、勤務時間の短縮や効率的な運営ができるようになるでしょう。
【3】点呼が優遇される
2つの地点間を定時で運行する流れの場合、他の営業所における点呼や同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が、Gマーク認定を受けることで承認されるようになります。これにより、業務の効率化ができるようになるのもメリットの1つです。
【4】安全性優良事業所として表彰される可能性がある
連続してGマークを10年以上取得しており、国が定める評価基準をクリアした場合、さらに一定の高いレベルにある「安全性優良事業所」として表彰される可能性があります。
表彰には、運輸支局長表彰と地方運輸局長表彰の2種類があり、表彰されることで、より自社の信用を高められるメリットが得られるでしょう。
【5】基準緩和自動車の有効期間の延長
基準緩和自動車が適切に運行されている事業所が、Gマーク認定を受けた場合、基準緩和自動車の有効期間が無期限に延長(通常4年間)されるメリットがあります。
【6】特殊車両通行許可の有効期間の延長
特殊車両の通行許可について、Gマーク認定を受けているほか、一定の要件を満たす優良事業所は、有効期間が通常2年間から最長4年間まで延長されます。
対象となる優良事業者の車両の要件は、下記のとおりです。
- 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であること
- 違反履歴のない事業者の車両であること(過去2年以内に違反の履歴がない)
- Gマーク認定事業所に所属する車両であること
上記のように、Gマーク認定を受けた事業所は、国からさまざまなインセンティブを受けられるメリットがあります。
日本トラック協会から得られる4つのメリット

Gマーク認定事業所は、日本トラック今日からも下記のメリットが得られます。
- ドライバー等安全教育訓練促進助成制度の優遇
- 安全装置等導入促進助成事業の優遇
- 経営診断受診促進助成事業の優遇
- 自動点呼機器導入促進助成事業の優遇
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
【1】ドライバー等安全教育訓練促進助成制度の優遇
ドライバー等安全教育訓練促進助成金制度は、トラックドライバーや安全運転管理者などが安全教育訓練を受講する際に、その費用の一部を助成する制度です。
Gマーク取得により、特別研修の受講料助成金が、通常7割のところ全額に増額となるメリットが得られます。
【2】安全装置等導入促進助成事業の優遇
安全装置等導入促進助成事業とは、安全運転を支援する装置で協会の助成の対象となるものを導入した場合、導入にかかる費用の一部を助成する制度です。
Gマーク取得により、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する、携帯型アルコール検知器を1台につき、2分の1(上限2万円)の助成が可能となります。
【3】経営診断受診促進助成事業の優遇
経営診断受診促進助成事業とは、経営改善に取り組む事業者が経営診断を受ける際に、経営診断費用の一部を助成する事業です。
Gマーク取得により、下記の助成を受けることができるようになります。
- 経営診断助成金:通常8万円が10万円に増額
- 経営改善相談助成金:通常2万円が3万円に増額
経営診断や相談を検討している事業所は、活用してみてはいかがでしょうか。
【4】自動点呼機器導入促進助成事業の優遇
自動点呼とは、ロボットやICT機器を活用して自動化するシステムのことであり、自動点呼機器導入促進助成事業とは、国土交通省が認定した製品を導入する中小事業者を対象に、導入費用の一部を支援する制度です。
Gマーク取得により、導入できる台数の上限が、通常1事業者1台のところ2台まで緩和されます。さらに、助成額の上限が、通常1台あたり上限10万円が2台分で上限20万円増額されるメリットが受けられます。
損保会社から得られるメリット

損害保険会社及び交通共済の一部では、Gマーク認定業者の運送保険等において、独自の保険料割引を適用しています。
保険料割引を適用している会社は下記のとおりです。
- あいおいニッセイ同和損保
- 損害保険ジャパン
- 東京海上日動火災保険
- 神奈川県自動車交通共済協同組合
- 四国交通共済協同組合
- 近畿交通共済協同組合
- 日本貨物運送協同組合連合会「日貨協連 新貨物補償制度」
詳しい割引率や内容は、各保険会社に確認しておきましょう。
Gマーク認定【4つのデメリット】
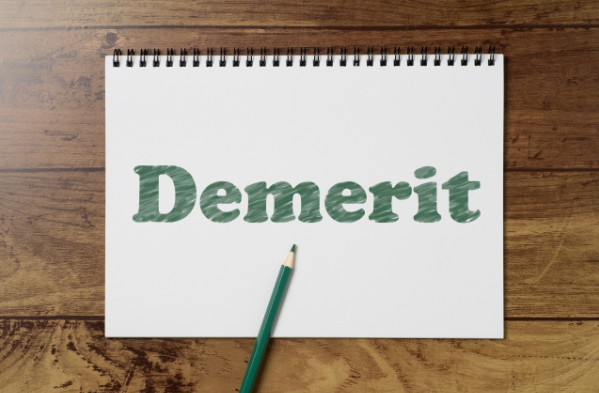
Gマーク認定を受けるメリットは大きいですが、取得することでデメリットに感じることもあります。具体的には下記の内容がデメリットとして挙げられます。
- Gマーク認定申請のために膨大な資料作成が必要になる
- 適正な帳票管理や報告などで事務負担が大きくなる
- 安全性向上に向けた取り組みのために時間が必要になる
Gマーク認定を受けるための申請に必要な書類の作成だけでなく、日報や点呼簿などの帳票類を適切に管理する必要が出てきます。そのため、事務担当者への負担が大きくなることや、資料作成のための人員確保がデメリットになるでしょう。
また、安全性向上に向けた取り組みの成果は、時間がかかることも理解しておく必要があります。
Gマーク認定の申請資格や条件・流れ
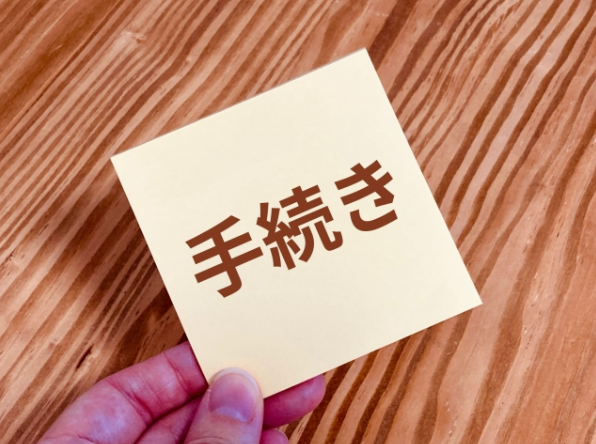
この章では、Gマーク認定の申請資格や条件について解説し、申請から取得までの流れもご紹介します。
申請資格
Gマーク認定の申請には、下記の資格を満たしている必要があります。
- 事業(運輸)開始から3年を経過していること
- 事業用自動車の配置数が5両以上であること
- 過去に行政処分を受けてから3年を経過していること
また、Gマークの不正申請や偽造などにより、是正勧告や申請却下、取り消しとなった過去がある場合、下記の年数を経過している必要があるので、ご注意ください。
- 不正申請により申請の却下や評価・認定の取り消しを受けている場合:2年以上
- Gマーク認定証やGマークステッカーの偽造による是正勧告を受けた場合:偽造したGマーク認定証等を提出した日から3年以上
是正勧告や申請却下、取り消し後に再申請される場合は、勧告や通知を受け取ってから、必要年数を経過しているかを確認しておきましょう。
認定条件
Gマークの認定には、評価項目の点数の合計点が100点満点中80点以上であることが条件となっています。さらに、各評価項目で下記の基準点数を満たしていることが必要です。
- 安全性に対する法令の遵守状況:40点満点中32点
- 事故や違反の状況:40点満点中21点
- 安全性に対する取組の積極性:20点満点中12点
上記に加えて、4つの自認項目グループすべてで得点する必要があります。
ほかにも、法に基づいた適正な申請、届出、報告がされていることや、適正な社会保険等への加入がされていることも条件になっています。
認定までの流れ
Gマーク認定までの流れは下記のとおりです。
- 安全性への対策や取組の実施と資料の作成
- 申請書を作成と申請
- 地方適正化実施機関に必要書類を提出
- 地方適正化実施機関から全日本トラック協会へ必要書類を送付
- 全日本トラック協会の安全性評価委員による評価・認定のあと公表
上記の流れを経て、Gマーク認定がおります。
Gマークに関する気になる質問

この章ではGマーク認定に関する気になる質問を、3つ厳選してご紹介します。
- Gマーク認定の申請にかかる費用や期間は?
- Gマーク認定が取り消しとなる理由は?
- Gマーク認定は有効期限がある?
それぞれの質問内容を詳しく見ていきましょう。
Gマーク認定の申請にかかる費用や期間は?
Gマーク取得にかかる費用は、インターネット申請を利用して提出するのか、紙で提出するかによって異なります。費用の違いは下記のとおりです。
- インターネットで申請書を作成する場合:無料
- 紙で申請する場合:複写式申請書の購入に1,000円ほど必要
Gマーク認定の申請から結果発表が出るまでの期間は、約5か月かかります。申請の受付期間は、毎年7月初旬から中旬(おおよそ2週目末頃)までとなっており、必ず期間内に申請の受付を済ます必要がある点に注意が必要です。
Gマーク認定が取り消しとなる理由は?
国土交通省「評価・認定制度の全体概要(案 )」によると下記の①〜⑤のいずれかに該当する場合に、Gマーク認定が取り消しされると定められています。
| ① 不正申請等により、評価・認定を受けたことが確認された場合
② 有効期間内に、死傷事故が発生した場合 ③ 有効期間内に、死傷事故、転覆等の事故又は悪質違反による事故が発生した にもかかわらず、30日以内に実施主体に報告しなかった場合 ④ 有効期間内に、車両停止以上の行政処分を受けた場合 ⑤ A を有する事業者において、有効期間内に、転覆等の事故又は悪質違反によ る事故が発生し、(3)の再評価の結果(※)、一定の基準点未満の場合 |
引用:国土交通省「評価・認定制度の全体概要(案 )」
※(3)の再評価の結果とは、⑤に掲げる事故が発生した場合、当該事業者の希望により、事業者に対して再評価を行うことです。
Gマーク認定は有効期限がある?
Gマークの有効期限は2年間です。具体的には、Gマーク認定を受けた年から2年後の12月31日までとなっています。
有効期間前に、全国トラック協会から更新案内のハガキが運送事業に郵送されるので、更新を忘れないようにしておきましょう。
Gマークの取得は多くのメリットが得られる
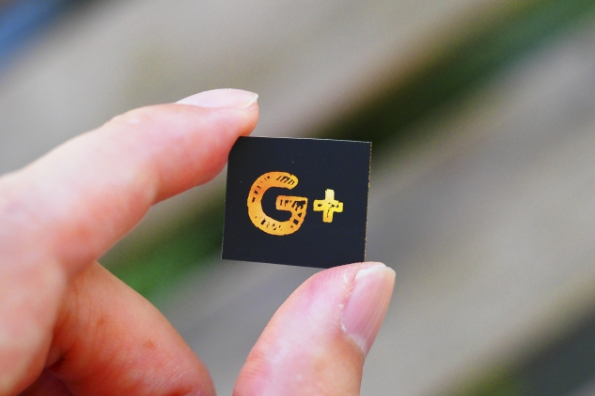
Gマーク認定を受けるための取り組みは、ドライバーの事故減少につながるほか、燃料費や保険料の割引などの経費削減のメリットが得られます。また、Gマーク認定を受けることで、荷主からの評価も高くなり、選ばれやすい事業所になるでしょう。
さらに、国土交通省や日本トラック協会からもさまざまなインセンティブを受けられます。
ただし、Gマーク認定を受けるための申請準備や取り組みなどに、手間や時間が取られるのがデメリットです。
しかし、Gマーク認定業者になることで得られるメリットは大きいでしょう。
もし、質の高いドライバーの募集を検討しているなら、全国に対応している求人・転職サービスの「ドラピタ」に掲載がおすすめです。
「ドラピタ」では、ドライバー案件に特化した職種軸で検索が可能なため、貴社の狙ったターゲットへ求人原稿を訴求できます。
掲載について詳しく知りたい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。