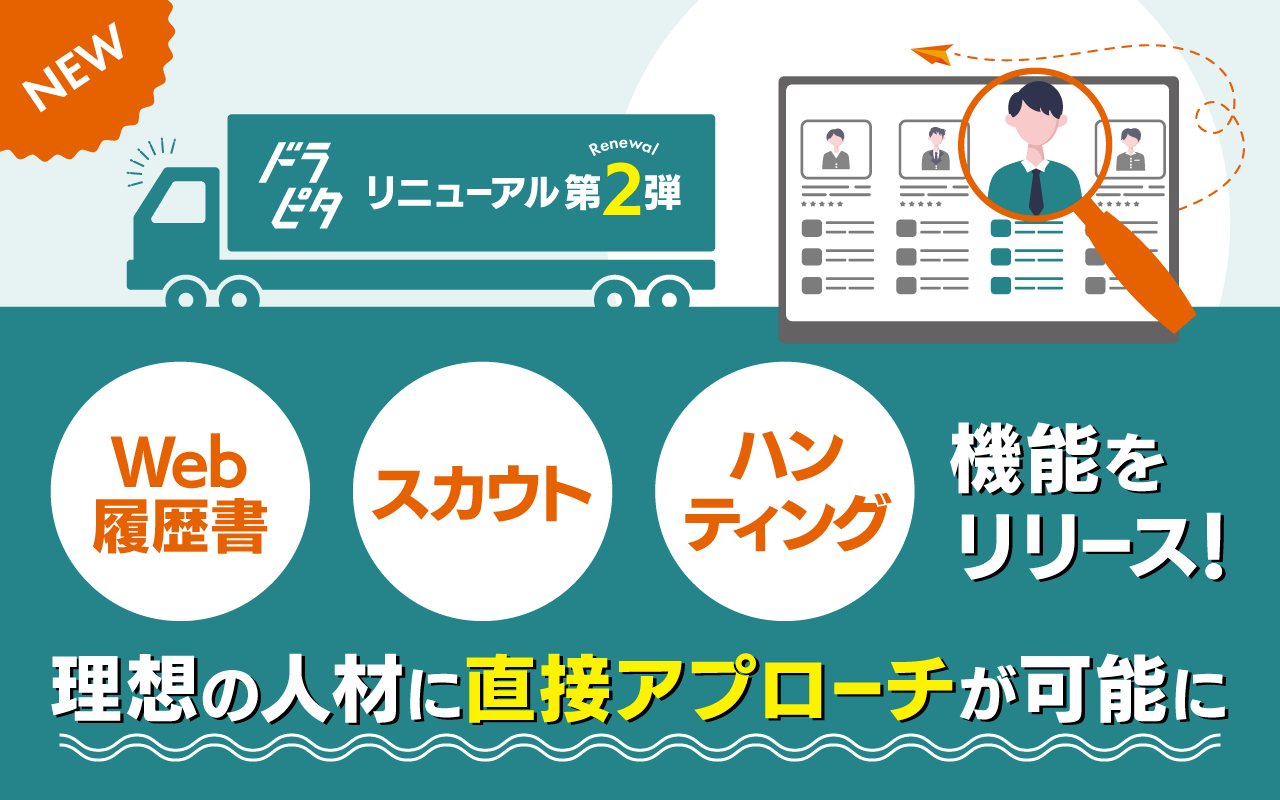少子高齢化が進むなか、物流業界の未来を支える「共創物流」に注目が集まっています。共創物流は、企業同士が協力し効率化を図る新たな取り組みです。
本記事では、共創物流の仕組みや重要性、具体的なメリットや成功事例、解決すべき課題を解説します。
物流業界のドライバーや管理職の方は、業務効率化の参考にしてください。
共創物流とは?

共創物流とは、企業同士が協力して物流プロセスの効率化を図る仕組みです。
これまでは企業ごとに独立して輸送を行っていましたが、車両や倉庫、データを複数の企業間で共有して効率化を目指しています。企業間の連携によって物流の効率を上げ、コスト削減と環境負荷の軽減を目指すのが共創物流です。
現在は一部の企業同士で進められていますが、将来的には物流業界全体の変革を促す重要な取り組みといえます。
共創物流が必要な理由

現在の物流業界では、以下のような問題が深刻化しています。
- ドライバー不足が深刻化している
- 物流コストが増加している
- 物流環境が複雑化している
- 環境への負荷が大きくなっている
近年トラックドライバー不足が深刻化しているので、共創物流による効率化が急務になっています。
ドライバー不足が深刻化している
日本では少子高齢化が急速に進行しており、働き手となる若年層の人口が減少しています。2022年の経済産業省・国土交通省・農林水産省の資料には、以下のような記載がありました。
「トラックドライバーについては、労働環境(労働時間、業務負荷等)から人材確保が容易ではなく、全産業に比して、平均年齢が3~6歳程度高い」
引用:経済産業省・国土交通省・農林水産省|我が国の物流を取り巻く現状と取組状況
物流業界と他の業界と比較すると、20代から30代のトラックドライバーの割合が極端に少ないことがわかっています。このような状況下で新規採用は難しく、既存のトラックドライバーへの依存が続いているのが現状です。
特に、地方の中小規模の運送会社ではトラックドライバーの確保が困難なため、配送が遅延したり、一人当たりの労働時間が増加したりするなどの悪循環が発生しています。
労働時間の増加は働き手の離職率を高める要因となり、さらなる人材不足を引き起こしています。
物流コストが増加している
輸送コストの増加も、物流業界の大きな課題です。2022年から2023年にかけて、燃料費が国内で高騰し、輸送コストを押し上げました。これに加えて、インフレによる物価上昇が重なり、輸送コストや設備投資も増加しています。
さらに、従来の物流体制では、空車の状態での移動が発生してしまいます。特に、長距離輸送後に積み荷がない状態で拠点に戻る「片道輸送」は非効率そのものです。
燃料費や物価はさらに高騰しているため、今後も物流コストが上昇する可能性は十分あります。
物流環境が複雑化している
物流の複雑化も業界全体にとって大きな問題です。グローバル化にともない、物流プロセスが多岐にわたるようになりました。さらに、EC市場の急速な拡大によって、消費者が商品を求めるスピードが早くなっています。
当日配送や翌日配送の需要が高まり、複数の配送ルートを同時に管理する手間も増加しています。これに加えて、消費者が異なるサイズや内容の商品を注文するため、仕分け作業が煩雑化しているのも課題です。
環境への負荷が大きくなっている
国土交通省の2021年のデータによると、日本国内のCO2排出量のうち17.4%が運輸部門から発生していました。特にトラック輸送は大量の燃料を使用するため、環境負荷が高くなっています。
世界各国で地球温暖化対策が進む中、企業にとって環境への配慮は社会的責任となっています。共創物流の導入は、輸送車両の台数削減につながり、環境負荷を軽減できるのが特徴です。
参照:国土交通省|環境負荷軽減のための都市物流の先進事例と都市・交通政策に関する調査研究(中間報告)
共創物流を取り入れる3つのメリット

共創物流を取り入れることで、以下のようなメリットがあります。
- 業務効率化を促進できる
- 輸送コストの削減につながる
- CO2排出量を削減できる
特に、業務を効率化して職場環境を整えると、トラックドライバーの離職率も減少します。
業務効率化を促進できる
物流業界では、空車の移動や非効率なルート設定が生じやすい業界です。共創物流を導入すると、複数の企業が車両やドライバーを共有する仕組みを構築できるため、空車問題の解消やルートの最適化ができます。
例えば、異なる企業が同じ地域で配送を行っている場合、従来は各企業が個別に車両を運行させていました。
しかし、共創物流では、これらの配送業務を一本化し、共有車両を効率的に運用します。その結果、空車移動の回数が減って輸送効率が向上するのがメリットです。
さらに、物流拠点の統合やデータ管理の一元化も、業務効率化に大きく貢献します。
管理システムを活用した配送ルートの最適化によってリアルタイムでの配送状況把握が可能となり、急な計画変更への対応も実現します。
共創物流は単に業務を効率化するだけではなく、柔軟な対応で顧客満足度の向上にもつながるのが特徴です。
輸送コストの削減につながる
物流業界において、輸送コストは企業経営における大きな負担です。燃料費や人件費の高騰に加え、非効率な長距離輸送がコスト増を引き起こしています。
共創物流を導入すると、輸送コストを大幅に削減可能です。たとえば、A社とB社が同じエリアに荷物を配送する場合、従来であれば2台のトラックを運行させる必要がありました。
しかし、共創物流ではこれを1台のトラックに荷物を集約できます。この「共同配送」によって燃料費が削減されるだけではなく、ドライバーの労働時間も短縮されます。特に地方や遠隔地への輸送では、荷物が少なく非効率な輸送が問題でした。
共創物流では、複数企業の荷物をまとめてトラックの積載効率を向上させ、輸送費を最小限に抑えます。共創物流は企業の収益を高めるだけではなく、運送費の低減によって顧客にもメリットをもたらします。
CO2排出量を削減できる
物流業界は、環境負荷の軽減という社会的責任を果たす必要があります。日本のCO2排出量の17.4%を運輸部門が占め、その大部分がトラック輸送によるためです。
共創物流を導入すると、複数企業が個別にトラックを運行する必要がなくなります。これまで10台のトラックで配送していた荷物を5台に集約できれば、単純計算でも燃料消費量を半分に減らせます。
共創物流は企業の社会的評価を高め、環境配慮型のビジネスモデルを構築するきっかけにもつながる取り組みです。
共創物流の取り組み事例

すでに共創物流に取り組んでいる企業の事例として、以下の3つの事例を紹介します。
- 大手食品メーカー5社の取り組み
- ヤマト運輸と西東京バスの取り組み
- 大手コンビニ3社の共同配送の取り組み
特にヤマト運輸と西東京バスの取り組みは、お互いの利益増加につながっています。
大手食品メーカー5社の取り組み
食品業界では、従来、メーカーごとに独自の物流体制が構築されていましたが、その非効率性が問題視されていました。
そこで、以下の5社が共同で物流標準化を進めるプロジェクトを立ち上げました。
- 味の素
- ハウス食品グループ
- カゴメ
- 日清製粉ウェルナ
- 日清オイリオグループ
この取り組みでは、納品伝票やパレットの規格、外装サイズやコード体系の統一を実現しました。その結果、トラックへの積み込みや倉庫内での取り扱いが簡略化され、作業時間の短縮に成功しています。
また、5社が共同配送を行うことで配送トラックの稼働台数を削減し、燃料費や人件費の削減にもつながっています。
さらに、企業間でのデータ共有によって配送ルートの重複を解消し、より効率的な輸送計画が立案されました。
上記5社の取り組みは、食品業界全体での物流効率向上のモデルケースとなり、他業界でも注目されています。
ヤマト運輸と西東京バスの取り組み
ヤマト運輸と西東京バスは、物流業界と公共交通機関の連携という新しい試みとして「客貨混載」の仕組みを導入しました。この取り組みでは、バスの運行ルートを活用して荷物を配送先の最寄りバス停まで運び、そこからヤマト運輸のドライバーが荷物を最終目的地に届ける流れを確立しました。
客貨混載のメリットは輸送効率の向上だけではありません。
西東京バスは、従来の乗客輸送に加えて荷物を運ぶことで新たな収益源を確保でき、ヤマト運輸はトラックでの移動距離を短縮できるため、燃料費や人件費を削減できました。
また、バスを利用した輸送によって、CO2排出量の削減にもつながっています。
客貨混載の取り組みは、地方や山間部など物流効率が低い地域での課題解決策として注目されています。
大手コンビニ3社の共同配送の取り組み
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの大手コンビニ3社は、遠隔地への配送効率向上を目的とした共同配送の実証実験を実施しています。
地方の店舗は配送効率が悪く、輸送コストが高いという問題がありました。また、人口減少による「買い物困難者」の増加も課題として浮上しています。
コンビニ大手3社の取り組みでは、配送センター間の荷物を統合し、共通のトラックで地方店舗への配送を行う仕組みを構築しました。
これによってトラックの稼働台数を減らし、輸送ルートを最適化することに成功しています。共同配送はコスト削減だけではなく、地方の店舗への安定した商品供給を可能にしました。
今後もこの取り組みは拡大する予定で、物流業界全体における効率化の手本になると期待されています。
共創物流が抱える課題

メリットの多い共創物流ですが、導入する際には以下のような課題もあります。
- 物流プロセスやシステムの統合
- データの共有やセキュリティ面の対策
業界によって規格やデータ形式が異なるので、統合が難航しているのが現状です。
物流プロセスやシステムの統合
物流業界では、各企業が独自の配送プロセスや規格を採用しています。
例えば、商品を運ぶ際に使用するパレットの素材やサイズは、企業や業界ごとに異なるのが一般的です。ある企業では樹脂製パレットを使用している一方で、別の企業は木製パレットを使用しているため、物流プロセスの統一が難航しています。
さらに、トラックの積載量や倉庫内での取り扱い方法も企業ごとに違いがあるため、プロセスを統合するには多大な時間とコストがかかります。
一度に全ての企業が同じ規格に切り替えるのは非現実的なので、段階的な調整が必要です。
物流プロセスの標準化が進むと配送効率が向上し、共同配送の恩恵をより多くの企業が享受できます。
そのためには、政府や業界団体による規格の統一推進や、補助金を活用した移行支援が求められています。
データの共有やセキュリティ面の対策
共創物流では、配送スケジュールや在庫状況などのデータを企業間で共有する必要があります。しかし、データを共有する際はセキュリティリスクがともないます。
特に、機密情報の漏洩や不正アクセスは、企業にとって大きな経済的損失や信用失墜につながりかねません。輸送中の荷物の位置情報や取引先の情報が外部に流出すると、競合他社に不利な情報が伝わる危険性があります。
さらに、サイバー攻撃によるデータ改ざんやシステム停止も企業にとって深刻な問題です。
これらのリスクに対処するためには、堅牢なセキュリティシステムの導入が不可欠です。
暗号化技術の活用、アクセス権限の厳格な管理、AIを活用した不正アクセス検知などが有効な対策となります。
また、各企業が個別にセキュリティ対策を行うだけではなく、共創物流に関わるすべての関係者が共通のセキュリティ基準を策定し、遵守することが重要です。
さらに、データ共有の利便性を高めるためには、業界全体で利用できる共通プラットフォームの構築も必要です。このプラットフォーム上で、リアルタイムの情報共有やトラブル発生時の迅速な対応が可能になれば、共創物流の信頼性が大きく向上するでしょう。
共創物流は中長期的に物流を支える重要な取り組み

共創物流は異なる企業間でトラックやドライバーを共有し、物流効率を高める重要な取り組みです。
輸送効率が高くなるため、トラックドライバーの長時間労働を減らし、離職率を下げる効果も期待されています。
業務の効率化やコスト削減を考えている経営者は、共創物流で新しい物流の仕組みを作ってみましょう。
トラックドライバーを募集している企業は、物流業界に特化した転職サイト「ドラピタ」で即戦力となる人材を雇用してみませんか?
トラックドライバーの雇用は、多くの運送会社の課題となっています。
物流業界に特化した「ドラピタ」を活用して、スキルを有した新たな人材を探してみましょう。