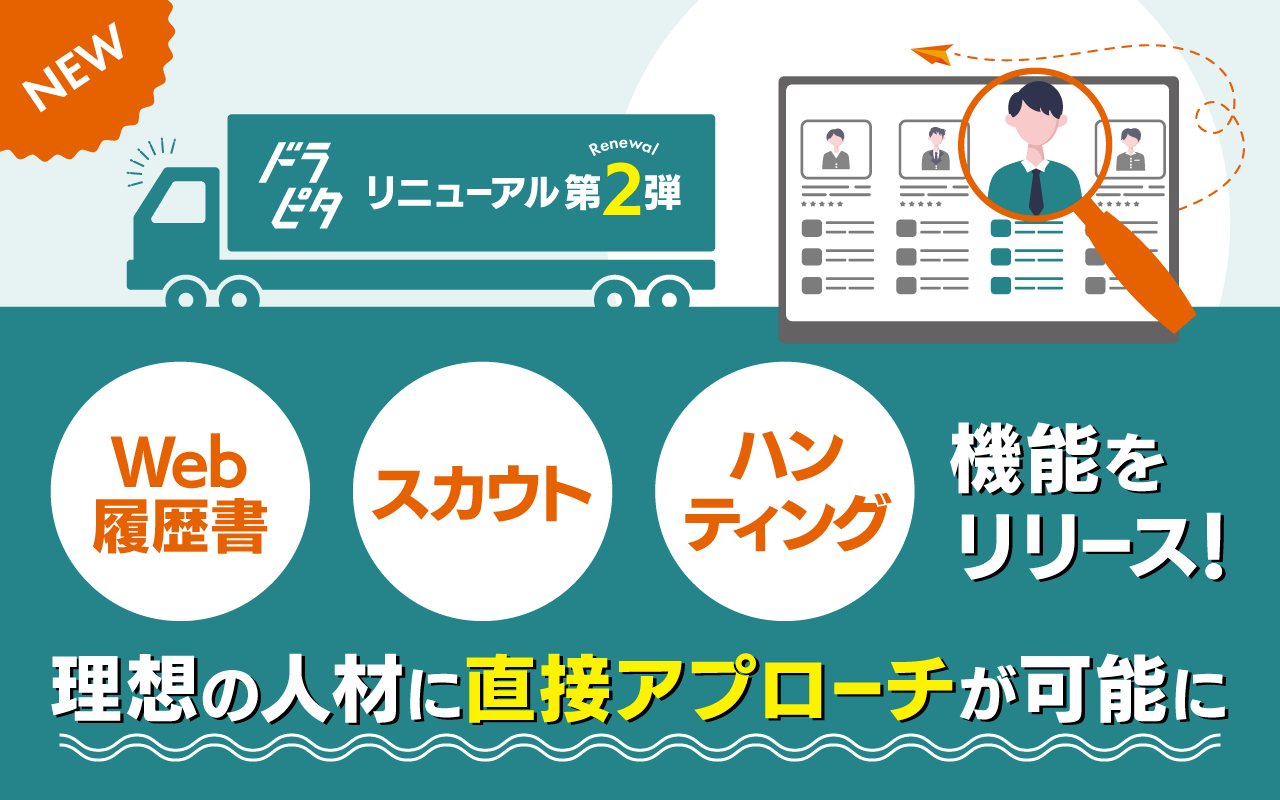ラストワンマイルとは、物流業界における特定の配送区間を指します。現在、ラストワンマイルでは、ドライバー不足や再配達の増加などのさまざまな課題が見られます。
ラストワンマイルの課題に対応しないと、物流コストや時間が増加し、サービス低下を招きかねません。
本記事では、ラストワンマイルの仕組みや市場規模の変化、解決策を紹介します。
ラストワンマイルの配送を担当している方は、本記事を改善策の参考にしてください。
物流のラストワンマイルはセンターから消費者までの最後の配送区間

ラストワンマイルとは、商品が保管されている拠点から消費者の元へ届ける最終区間を指す言葉です。主に宅配便のドライバーがラストワンマイルを担当します。
この区間は消費者と直接顔を合わせる機会が多いため、顧客満足度を左右する重要なポイントです。
ECサイトでの買い物が普及した現在は、商品の注文から手元に届くまでのスピードが重視されるようになり、ラストワンマイルの需要が増加しています。
その一方で、都市部での交通混雑や再配達の多発などの理由から、効率的に消費者に荷物を届けるのが困難になっています。
物流のラストワンマイルで起きている問題

ECサイトやインターネットのショッピングモールの拡大にともない、ラストワンマイルには以下のような負担がかかっています。
- 配送するドライバー不足
- ECの普及による業務量の増加
- 再配達の増加
- 送料無料の弊害
特に、配送ドライバーの不足は、荷物の到着遅延やサービス低下につながる深刻な問題です。
配送するドライバー不足
少子高齢化の影響は物流業界にも及び、配送に携わるドライバー不足が年々深刻になっています。特に、トラックを運転するドライバー人材が減少傾向で、求人を出しても応募が少ない状況が増えています。
この状況は宅配業務にも直結し、時間指定に間に合わない、到着予定日がずれるなどのトラブルにつながりかねません。企業によっては宅配ドライバーの長時間労働が常態化し、負担がさらに増大する悪循環に陥っています。
深刻なドライバー不足を解決しない限り、ラストワンマイルの安定とサービス向上も難しくなっています。
ECの普及による業務量の増加
Amazonや楽天のような大手のショッピングモールだけではなく、近年は独自のECサイトを立ち上げる企業も増えています。
ECサイトが増加している影響で、消費者へ届ける宅配便の個数も右肩上がりになっています。国土交通省のデータによると、令和5年度の宅配便取扱個数は50億733万個にのぼり、前年から145万個増加しました。
荷物が増えれば増えるほど、配達が遅れたりドライバーの勤務時間が延びたりするリスクが高まっています。
ECサイトの普及による業務量の増加は、ラストワンマイルを支えるドライバーの負担増加につながっています。
参照:国土交通省|令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について
再配達の増加
国土交通省の調査によると、令和6年10月時点での再配達率は10.2%に達しました。荷物を10個届ければ、そのうち1個は再配達になってしまう計算です。
再配達はドライバーの労力が増加するだけではなく、燃料消費や二酸化炭素排出量の増加にもつながります。
消費者の生活が多様化し、忙しくて荷物を受け取れない時間帯が多いことも再配達が増えている原因です。
しかし、再配達を減らす工夫をしないと、ラストワンマイルの効率はさらに悪くなってしまいます。現在、企業や行政が連携して再配達の改善を目指す動きが進められています。
送料無料の弊害
ECサイトやショッピングモールの中には、顧客獲得のために「送料無料」を打ち出しているケースがあります。消費者は送料無料になっても、配送コストは誰かが負担しなくていけません。
契約によっては無料分の送料を運送会社が支払うケースがあり、運送会社の収益が下がる原因になっています。運送会社が負担を強いられてしまうと、ドライバーの待遇改善や増員に投資する余裕を失い、人手不足を加速させてしまう懸念があります。
顧客が安く買い物を楽しめる一方で、無料になった送料の負担が重くなるのがラストワンマイルの課題です。
物流でラストワンマイルの市場規模が増加した背景

ラストワンマイルの市場規模が増加したのは、ECサイトの利用者が増加したことにくわえ、新型コロナウイルスの流行によって外出を控える動きが広がったことも要因となりました。
外出自粛期間に自宅で買い物が完結するメリットを多くの消費者が体験し、自粛期間が終わった現在もECサイトの利用者は増加しています。
さらに、インターネット環境の整備も相まって宅配需要が一段と高まりました。実店舗の営業時間に左右されず好きなときに注文できる利便性が浸透した結果、大量の荷物がラストワンマイルを通過するようになりました。
今後もECサイトでの商品購入が進むかぎり、ラストワンマイルの市場規模は拡大を続けるとみられています。
物流のラストワンマイルにおける課題を解決する方法

ラストワンマイルの課題を解決するためには、以下のような取り組みでドライバーの負担を軽減する必要があります。
- 宅配荷物の受け取り手段を増やす
- 管理システムを導入する
- 配送手段を増やす
- 配送の自動化に取り組む
- 消費者の行動変容を促す
特に近年は、荷物の受け取り手段を増やすための施策が次々に実施されています。
宅配荷物の受け取り手段を増やす
ドライバーがすべての荷物を対面で手渡しするのは、現実的に厳しくなっています。
そこで、以下のような手段で荷物の受け渡しを効率化する動きが加速しています。
- 宅配ロッカーや宅配ボックス
- 置き配
- 店頭受け取り
駅やコンビニの敷地内に設置される宅配ロッカーは、消費者が都合の良い時間に取りに行けるのがメリットです。
自宅や玄関横に設置する宅配ボックスは、消費者が在宅していなくても安全に荷物を受け取れる効果的な仕組みです。宅配ボックスを設置して置き配を許可すると、ドライバーは不在の荷物を抱えるリスクが減少します。
また、運送会社の支店で消費者が直接荷物を受け取ると、荷物を配送するドライバーの移動時間を削減できます。消費者はその分送料が安くなるため、双方にメリットがある受け渡し方法です。
管理システムを導入する
効率的な運用を目指すためには、管理システムの導入が欠かせません。配達ルートを自動で組み立てたり、ドライバーの稼働状況を一元管理したりできると、業務を効率化できます。
再配達や急な日時変更への対応も、システム上で調整すれば効率良く対応できます。
管理システムを導入すると、属人化しがちだったルート選定から脱却できるため、業務効率化を図りたい企業にとってメリットです。
配送手段を増やす
近年は、トラックだけに配送を頼らず、自転車や台車を活用する運送会社が増えています。
特に道路が混雑している都市部では、トラックが駐車スペースを探すよりも自転車や台車のほうがスムーズに荷物を届けられます。
運送会社同士で共同輸送を行う動きも増えたため、荷物をまとめて運ぶことでドライバーの負担や走行距離の減少を目指しています。
こうした柔軟な配達手段の選択は、ラストワンマイルの業務効率化に欠かせません。
配送の自動化に取り組む
人手不足の緩和を目的に、ロボットや自動運転車両を活用する動きが進んでいます。
ヤマト運輸や日本郵便では、自動運転技術を使った配送の実証実験を積極的に行っています。現在、実証実験は限られた地域や企業のみが行っているなど限定的な施策です。
しかし、将来的には法改正によって、安全性を確保しつつ自動運転車が公道を走るケースが増え、ドライバー不足の解消に大きく役立つと予測されています。
消費者の行動変容を促す
国土交通省は、ラストワンマイル問題を改善しようと、官民連携で再配達削減を呼びかけるキャンペーンを実施しています。
2024年4月には「再配達削減PR月間」と位置づけ、荷物を柔軟に受け取ってほしいと広報活動を行いました。
消費者が受け取り方を工夫すると、再配達率が下がってドライバーの負担も減ります。
宅配ロッカーを利用したりコンビニ受け取りを選択したりする行動が広がると、ラストワンマイルの負荷が軽減します。
ラストワンマイルの改善事例

ラストワンマイルに関する課題を解消するため、さまざまな企業が以下のような工夫を凝らしています。
- 宅配ロッカーの設置
- 宅配ボックスの設置
- コンビニ受け取りの促進
- ドローン配送の実施
- ロボット配送の実施
企業が実践しているラストワンマイルの改善事例を紹介します。
宅配ロッカーの設置
宅配ロッカーは、駅やスーパーなどの大型施設に設置されている荷物専用のロッカーです。
消費者は事前に通知されたパスワードやQRコードを使い、好きなタイミングで荷物を受け取れます。
ヤマト運輸や佐川急便、楽天などがすでに宅配ロッカーを導入しており、駅ナカやスーパーの出入り口で荷物を受け取る消費者も増えています。
一度に荷物を配達できる宅配ロッカーの普及は、再配達の回数を減らしてドライバーの業務量を削減するために効果的な施策です。
宅配ボックスの設置
宅配ボックスは、郵便ポストに入らないサイズの荷物を受け取る専用ボックスです。宅配ボックスは壁に取り付けるタイプから簡易的に設置できる直立タイプまで、さまざまな種類が販売されています。
玄関前に荷物を直置きされるのが不安な消費者でも、鍵付きの宅配ボックスなら盗難を心配せずに置き配を指定できます。
宅配ボックスは防犯面のメリットも大きいので、留守が多い方ほど導入のメリットが大きくなる施策です。
コンビニ受け取りの促進
ECサイトで商品を注文するときに、最寄りのコンビニで受け取りできる仕組みが「コンビニ受け取り」です。ドライバーはコンビニへまとめて荷物を運び、消費者が都合のいいタイミングでコンビニまで荷物を取りに行きます。
コンビニは夜遅くても営業しているので、帰宅が遅い消費者でも確実に荷物を受け取れ、ドライバーは一度に複数の荷物を配達できるため効率が良くなります。
店頭受け取りの促進
店頭受け取りは、運送会社が運営する店舗や営業所で荷物を受け取る方法です。ドライバーが各家庭へ配達しなくて済むので、往復の手間が削減できます。
消費者は宅配便料金が割安になるケースもあるため、コストを抑えたい方にとって魅力的な受け取り方法です。店頭受け取りは移動時間の減少にもつながるので、渋滞や環境への負荷軽減にも貢献できます。
ドローン配送の実施
小型無人飛行機のドローンを使った配送は、ラストワンマイルを変革する新たな試みとして注目されています。ドライバーが移動しなくても無人で荷物を届けられるため、遠隔地や交通の便が悪いエリアでのメリットが大きい配送方法です。
現在、ドローンの実用化に向けて法規制や安全性の確認が進められており、一部の地域で実証実験を行っています。
今後、ドローンの実用化が進めば、物流の新しい形として定着する可能性が十分にあります。
ロボット配送の実施
楽天は4年間の実証実験を経て、2023年に茨城県つくば市でロボット配送サービスを展開しました(2025年1月時点では同市でのサービスは終了)。四輪の自走型ロボットが公道を移動するため、天候に左右されずに安定して荷物を配達できます。
ドライバーにとって負担の重く大きい荷物を運搬してくれるので、体への負担を軽減しやすい配達方法です。
法整備や技術開発がさらに進むと、ロボット配送は全国各地へ広がる可能性があります。
物流のラストワンマイルで注目されているシステム

ラストワンマイルを効率化するためには、以下のようなITシステムの存在が欠かせません。
- 倉庫管理システム(WMS)
- 輸配送管理システム(TMS)
特に代表的な倉庫管理システムと輸配送管理システムを紹介します。
倉庫管理システム(WMS)
倉庫管理システムは、倉庫内における在庫や作業を集中管理するシステムです。入荷した商品がどの棚に保管されているかを即座に把握し、ピッキングや梱包の流れをスムーズにします。システム主導で業務を進めるため、人的ミスが起こりにくいのが特徴です。
システムで集中管理できると出荷する荷物の管理も円滑になり、ラストワンマイルの配送遅延のリスクが減少します。
輸配送管理システム(TMS)
輸配送管理システムは、倉庫から配送先までの輸送状況を管理するシステムです。出発地と目的地を入力すると、最適なルートやスケジュールを提示してくれます。
ドライバーが手動でルートを作成するよりも効率が良く、属人的なノウハウに依存しない運用が可能になります。
万が一、交通渋滞や急なトラブルなどが起きても、システム上でリアルタイムに状況を確認して再配分を検討できるのが輸配送管理システムのメリットです。
物流のラストワンマイル問題の解決に取り組もう

ラストワンマイルの課題はドライバー不足、再配達、送料問題など多岐にわたります。
しかし、ドライバー不足の対策は確実に進んでおり、宅配ロッカーや管理システム、ロボット配送などが着実に導入されています。
効率的な仕組みを整えると、トラックドライバーにとっても働きやすい環境が期待でき離職率低下も見込めるでしょう。
配送ドライバーを募集している企業は、物流業界に特化した転職サイト「ドラピタ」で新たな人材を探してみませんか?
物流業界専門の転職サイトなので、ドライバーに興味のある人材とマッチングしやすいのが「ドラピタ」の魅力です。
ドライバー不足で悩んでいる企業は、「ドラピタ」で人材不足を解消してみましょう。