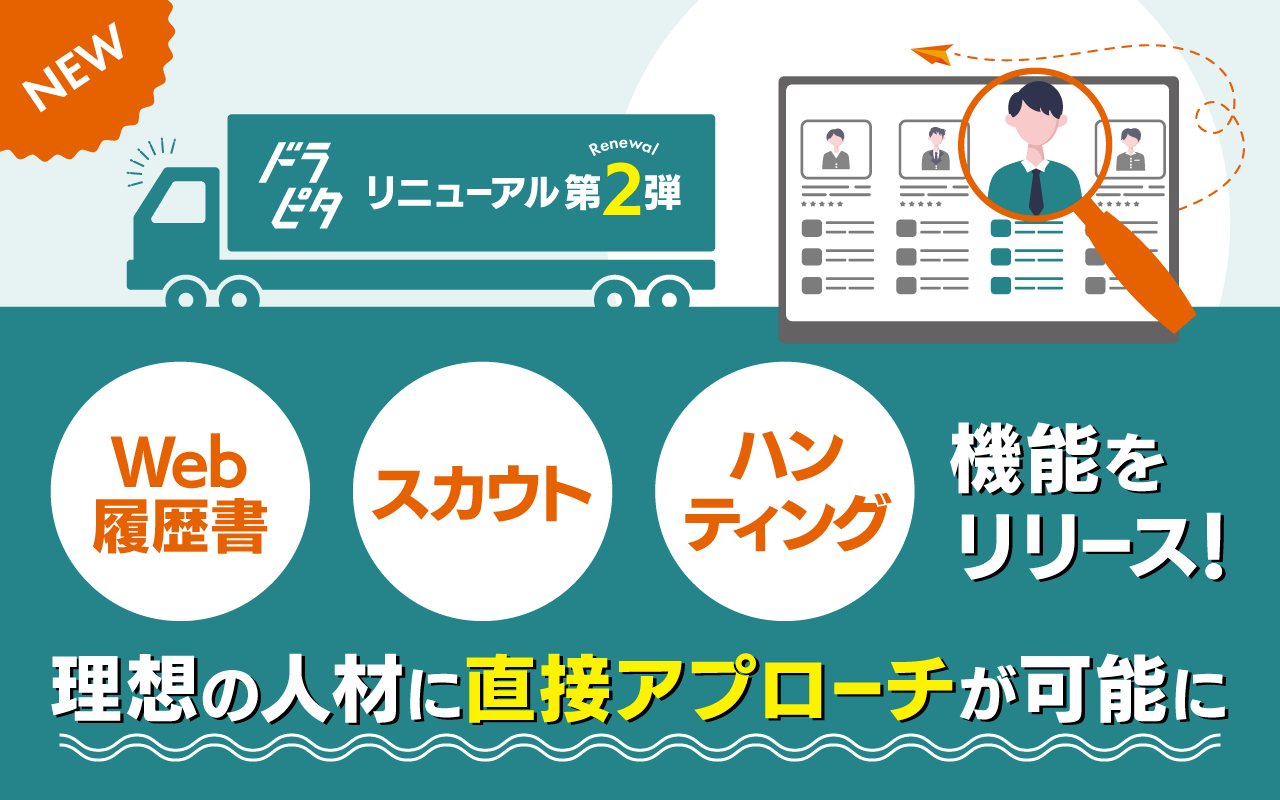運送事業を営む経営者にとって、下請法は従業員の労働環境や売上に直結する重要な法律です。
下請法の運用基準が2024年5月に改正され、荷主と運送事業者間の取引も新たに適用対象となりました。
本記事では、下請法の基礎知識・適用範囲・違反事項・改正後の変化を解説します。
下請法を正しく理解したい方は、本記事を参考にしてください。
2024年5月に改正された下請法とは?

下請法は、下請事業者を保護する目的で作られた法律です。
製品製造や役務の委託先が不利な扱いを受けないよう、公正な取引環境を実現するために制定されました。
公正取引委員会は2024年5月に運用基準を改正し、荷主と運送事業者の間に生じる委託取引も下請法の規制下に追加しました。
これにより、荷主からの受注形態や代金決定のプロセスなどが、下請事業者保護の観点で一層厳しくチェックされます。
元より運送業者は、過度なコスト削減や不当な返品、支払い遅延などのリスクにさらされやすいことが問題視されていました。
下請法の指針を踏まえて取引ルールを見直し、法令順守と効率的な運送体制を両立させることが大切です。
下請法の適用範囲と条件

運送業者が自社を守るためには、下請法の対象となる契約形態を整理しておく必要があります。
下請法の適用範囲と適用条件を解説します。
下請法の適用範囲
下請法の適用範囲は以下の通りです。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
運送業者は役務提供委託に該当するため、下請法の保護対象に入ります。
これまで、下請法は製造業が主な対象とされていましたが、今回の改正により、輸配送契約における不当な負担の押し付けや買いたたきなども規制対象となりました。
親事業者は複数の下請業者を抱えることも珍しくなく、その場合は特に仕事の安定性、報酬の適正性、契約の公平性の面で不適切な契約を結んでしまうことがあります。
契約条件や運賃・手数料の算定方法が適正に行われているかを確認した上で親事業者と契約を結ぶことが重要です。
運送業者に下請法が適用される条件
運送業者は、以下のケースに該当すると下請法が適用されます。
- 親会社(資本金1,000万円超~5,000万円以下)→下請事業者(資本金1,000万円以下)
- 親会社(資本金5,000万円超)→下請事業者(資本金5,000万円以下)
子会社を介する場合は以下の条件に該当すると下請法が適用されます。
- 親会社(資本金3億円超)→子会社(みなし親事業者)(資本金1,000万円以下)→下請事業者(資本金1,000万円以下)
下請法では、親事業者と下請事業者の資本金規模に基づき、適用の有無を判断します。
代表的なケースとして、親会社の資本金が1,000万円超〜5,000万円以下の場合、資本金1,000万円以下の運送事業者へ役務提供を委託する際には、下請法の適用対象となります。
また、親会社の資本金が5,000万円を超える場合は、資本金5,000万円以下の事業者との委託契約が下請法の対象です。
加えて、親会社が資本金3億円を超え、子会社(みなし親事業者)が資本金1,000万円以下のとき、その子会社がさらに資本金1,000万円以下の下請事業者へ再委託する場合も、下請法が適用されます。
運送業者は、自社の資本金区分と、荷主企業の資本金区分を把握して契約を結ぶ必要があります。
下請法違反となる主なケース11選

下請法違反となる主なケースは、以下の通りです。
- 受領拒否の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 報復措置の禁止
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
具体的にどんな事例が下請法違反になるのか、順番に解説します。
受領拒否の禁止
荷主が発注後に完成品やサービスの受領を拒む行為は、下請法違反に該当します。
運送業界では、荷主が急に運送依頼をキャンセルして費用を支払わないというトラブルがあります。
しかし下請法では、受領拒否は原則として認められません。
契約書面に明記された運送日時や荷物の詳細があるにもかかわらず、荷主側の都合で受取を拒否する行為は違反対象になります。
運送業者は、受注する際にキャンセル対応の条件や違約金の取り決めを明確にすることが大切です。
下請代金の支払遅延の禁止
配送が問題なく行われたにもかかわらず、支払期日を過ぎても代金が振り込まれない行為は違反となります。
支払い遅延は運送事業者の資金繰りを圧迫し、経営を不安定にしかねません。
下請法では、契約時に決めた支払期日までに全額を支払う義務があります。
また、支払遅延が生じた場合、親事業者は下請事業者に対し、当該未払金額に年率14.6%を乗せた額を遅延利息として支払う義務があります。
上記は、受領後60日を経過した日から支払する日までの期間が対象になるため、万が一支払い遅延が発生した場合は上記の金額を考慮して請求しましょう。
下請代金の減額の禁止
契約後に一方的に代金を下げる行為は、下請法で認められていません。
追加サービスを要求しながらその報酬分を反映しないケースや、「予想より経費がかかった」などの理由で報酬を減らすケースなどが該当します。
下請事業者の立場が弱いと、こうした一方的な減額要求を拒みにくい状況が発生しかねません。
しかし、下請法上、契約書面で合意した金額を守らない行為は違反に該当します。
返品の禁止
商品の返品を押し付ける行為も違反にあたります。
例えば、「発注品が不要になったから送り返す」という対応や、「輸送経路に問題があったから運送代金を払わない」などは不当とされます。
運送業では車両手配や燃料費、人件費など大きなコストがかかっているため、荷主側の勝手な理由で返送を要求されると損害が発生するためです。
正当な責任範囲を超えた返品指示が来た場合は、安易に要求を飲まないようにしましょう。
買いたたきの禁止
下請事業者が提供するサービスに見合わない低価格で契約を結ぶ行為も、買いたたきと呼ばれ下請法で禁止されています。
過度な買いたたきは下請事業者の経営基盤を脅かし、運送業界全体のサービス品質も下げかねません。
契約時には運送距離や車両台数などを踏まえた適切な料金で合意することが大切です。
購入・利用強制の禁止
荷主が、自社の商品やシステムの購入を下請事業者に義務付けるケースは下請法違反です。
一例を挙げると、「この運送管理システムを導入しなければ契約しない」などの要望や、「特定のリース車両を利用しないと契約しない」などが該当します。
商品やサービスの必要性やコスト負担の検証もなく、一方的に導入を押し付けられるのは問題です。
報復措置の禁止
下請事業者が公正取引委員会へ通報や相談をしたことを理由に、契約打ち切りや取引量の激減などの不利益を与える行為は下請法違反です。
上記の行為は、問題を告発する意思を封じる狙いがあるため、業者間の力関係を利用した不公正な対応とみなされます。
実際に報復措置が行われると、下請事業者は正当な意見を主張しにくくなります。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
運送業では親事業者から車両や燃料を提供されることがあります。
その際、親事業者が原材料や部品などを有償で支給し、下請事業者から早期に対価を回収する行為は下請法で禁止されています。
上記は、下請事業者が運送サービスを提供する前に資金を先取りする形になり、経営を圧迫しやすいためです。
原材料費の早期決済を要求された場合は、下請法に抵触するかどうかを確認する必要があります。
割引困難な手形の交付の禁止
下請事業者に支払いをする際、現金や一般的な約束手形と比べて換金が難しい手形を渡す行為は下請法違反です。
受取人が銀行で割引できない手形や、極端に長期の決済期間を設定した手形を使うことが該当します。
また運送業者は車両維持費や人件費など毎月のコストが大きいため、資金調達がスムーズにできない手形を交付されると経営に悪影響を及ぼしかねません。
下請法改正後は、手形でのやりとりは注意して行いましょう。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
発注側が「仕事を続けたいなら協賛金を出せ」や「運賃の一部を返金しろ」と迫る行為は、下請法違反にあたります。
下請事業者の立場の弱みにつけ込み、金銭的負担を押し付けることは公正な取引とは言えません。
とりわけ運送業は車両への設備投資や人件費負担が大きく、余計なコストを上乗せされると経営を圧迫してしまいます。
発注元から不合理な要求があった場合は、下請法違反の疑いを検討しましょう。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
運送ルートや時間帯などの契約時に合意した内容を、親事業者が後から勝手に変える行為は規制対象になります。
加えて、一度納品した貨物を「別の場所に送ってほしい」と要求し、その費用を支払わないのも下請法違反です。
下請事業者は車両や人員を再手配しなければならず、余計なコストや手間がかかります。
契約書と異なる指示が出た場合には、追加報酬を検討する場を設けることが求められます。
運送業者の多重下請けが引き起こす問題

運送業界で慢性化している多段階の下請け構造は、以下のような問題を引き起こしています。
- 賃金格差と深刻な人手不足
- 慢性的な長時間労働
- 中小企業の経営難
特に、賃金格差と深刻な人手不足が大きな問題になっています。
賃金格差と深刻な人手不足
下請け階層が下がるほど売上単価も下がりやすく、従業員の賃金にも大きな差が発生しています。
特に、運送の最終段階を担う軽貨物ドライバーや個人事業主などは、運搬1回あたりの報酬が厳しい設定になりやすいのが問題視されています。
元請との賃金格差が広がると、若い世代が運送業界を敬遠する傾向が強まり、人手不足がより深刻化します。
経営者としては、安定した報酬体系を整え、従業員に長く働いてもらえる仕組みをつくることで人材不足を解消したいのが本音です。
運送業界の多重下請け構造を抜本的に見直し、フェアな料金設定を実現することが深刻化する賃金格差や人手不足の是正につながります。
慢性的な長時間労働
トラックドライバーは、長距離運行や積み降ろしの待機で拘束時間が長いのが問題視されています。
積み降ろしが遅れたり、倉庫の受入態勢が整っていないと、ドライバーは車両で長時間待機するしかありません。
一部の企業では、待機時間を休憩時間とみなし、残業代を支払わないケースが問題視されています。
長時間労働と低賃金が同時に発生すると、ドライバーのモチベーション低下につながるだけではなく、安全運行にも悪影響が及ぶ恐れがあります。
経営者は待機時間の削減策を講じ、拘束時間が給与に反映される体制を整えなければなりません。
中小企業の経営難
多重下請け構造で末端に位置する中小零細企業や個人事業主は、売掛金の未回収や運賃の買いたたきに直面しやすいのが現状です。
こうしたリスク要因が重なると倒産につながる可能性が高まり、業界全体の物流ネットワークにも悪影響を及ぼします。
株式会社東京商工リサーチの調査では、2023年の軽貨物運送業倒産は過去最多となり、3年連続で増加しています。
倒産が連鎖すると、発注側は荷物を運ぶ手段を失い、一般消費者の購買行動にも影響を及ぼしかねません。
下請法を守りつつ適正な取引条件を確保することが、業界全体の利益につながります。
参照:株式会社東京商工リサーチ|「2024年問題」直前の軽貨物運送業 倒産と休廃業・解散の合計が3年連続で過去最多
下請法の改正で運送業者に起きる変化

下請法改正は、親事業者だけではなく、下請事業者側にも以下のような変化があります。
- 管理規定の作成が義務化される
- 管理帳簿の作成が義務化される
- 荷待ち時間短縮の取り組みが進められる
管理規定や帳簿作成など、新しく追加された業務を解説します。
管理規定の作成が義務化される
2024年5月の改正で、大規模な元請企業は下請事業者を適切に管理するための社内規定を整備する必要が生じました。
運送業においても、荷主が複数の運送会社と取引をする際、その秩序を保つための管理規定を策定しなければいけません。
具体的には、委託内容や報酬基準を明確にし、違反行為が発生した場合の社内処分や再発防止策を盛り込む必要があります。
さらに、責任者の選任も求められ、規定内容が現場に浸透しているかを管理する仕組みをつくることが重要です。
管理帳簿の作成が義務化される
下請法の改正後は、「実運送体制管理簿」と呼ばれる帳簿の作成と1年間の保管が義務化されました。
取引先の運送事業者名、業務内容、支払い条件などを時系列で記録し、委託の実態を明確にします。
公正取引委員会による監査が入った場合、帳簿の有無や記載内容が厳しくチェックされる見込みです。
運送業者が委託される側の場合でも、親事業者から管理帳簿作成の協力を求められる可能性があります。
荷待ち時間短縮の取り組みが進められる
下請法の改正では、大手荷主に対して荷待ち時間を短縮する計画の策定と国への定期報告を義務付けました。
トラック到着時に長時間待機させる問題は、ドライバーの労働環境を悪化させる大きな要因です。
今回の改正により、その改善を図らない荷主は是正勧告を受け、勧告に従わない場合は社名公表や是正命令が出されます。
さらに命令にも従わない場合、最大で100万円の罰金が科されます。
荷主と運送事業者が協力し、出荷スケジュールの見直しや倉庫の予約システム導入などを推進して、待機時間を減らす取り組みが求められています。
運送業者は下請法を守り従業員が働きやすい環境を作ろう

下請法の改正をきっかけに、運送事業者が置かれている厳しい環境を再確認する機会が増えています。
下請法を遵守した職場環境を整えると、給与や労働環境を改善しやすく、新しい人材も集まりやすくなります。
即戦力となる人材を探している方は、物流業界専門の求人サイト「ドラピタ」がおすすめです。
従業員を守り、企業を持続的に運営するためにも、改正された下請法を遵守した経営を心がけましょう。