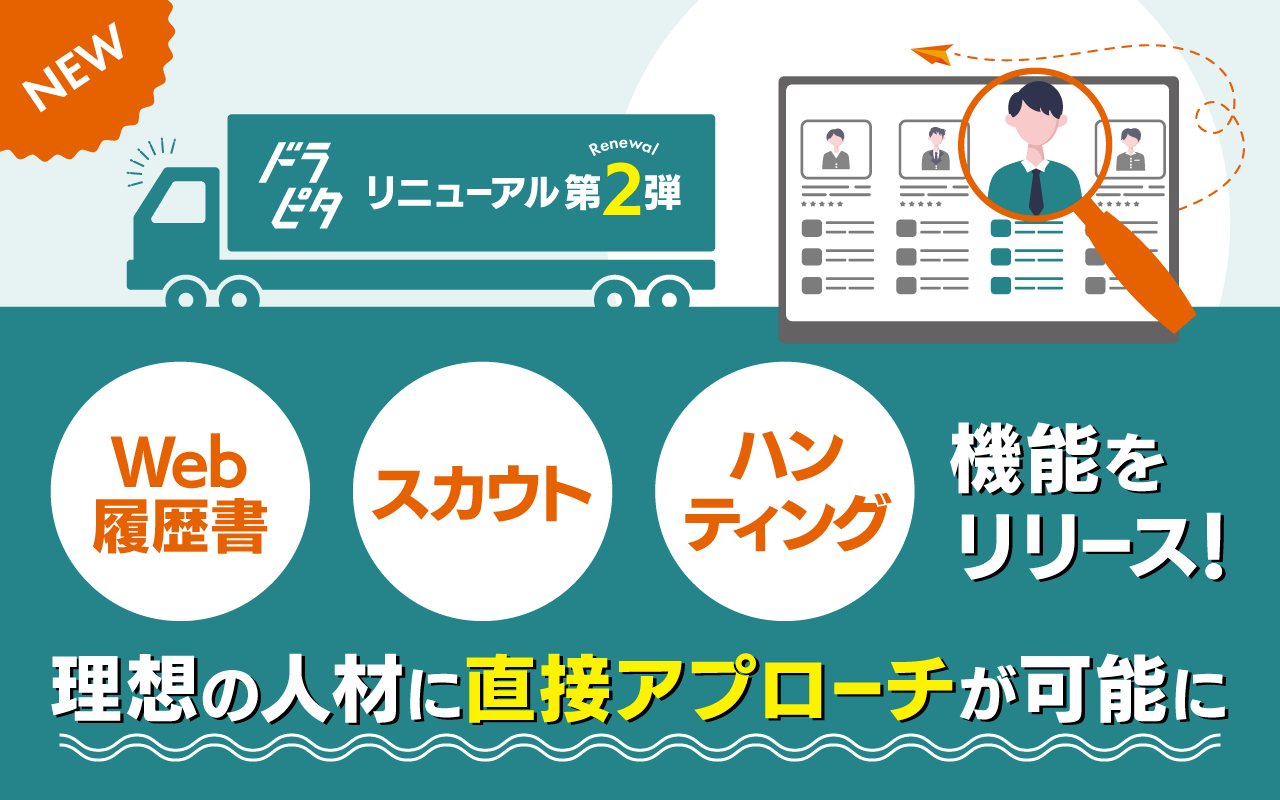運送業における下請法について徹底解説!法改正のポイントも紹介
運送業の下請法が2024年に改正されたことをご存じの方もいるでしょう。
下請法とは、下請企業の保護を目的とした法律です。
今回の改正では、どのような点が改正されたのか気になるところです。
そこでこの記事では、運送業における下請法について基本から改正ポイントまで詳しく解説します。
また、下請法の取締り対象となる「買いたたき」や「禁止行為」の事例もご紹介します。
自社の取引が下請法の対象になるかどうか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
運送業の下請法とは?

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、下請け企業の保護を目的とした法律です。
下請けとは、元請け企業が受注した仕事を、別の企業に委託することを指しています。
仕事の委託を受けた企業(下請け企業)は、元請け企業から指示された内容に従って業務を遂行するのが一般的な流れです。
また、トラック運送会社の99%以上は中小企業が占めており、特定の仕事に対して、複数の層にわたって下請け業者が関与する多重構造も一般的です。
下請法は、多くの下請け企業取引の公正化を図ることで、利益を保護する役割を担っています。
下請法の仕組み
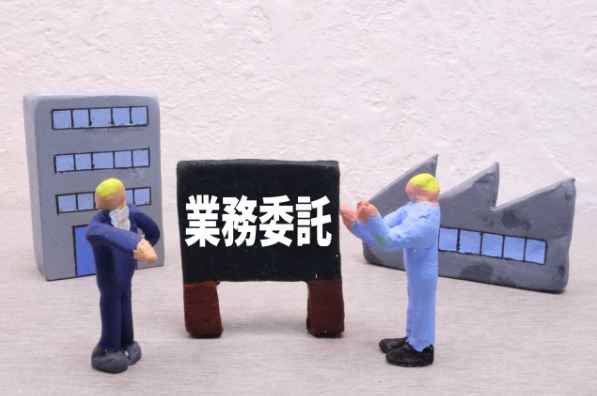
この章では、下請法の対象になる取引の範囲、運送業で対象となる役務提供委託について解説します。
自社の取引が、下請法の対象になるかどうか、ぜひ確認してみてください。
下請法の対象となる取引の範囲
下請法では、適用の対象となる下請取引の範囲を下記のとおり定めています。
- 取引当事者の資本金(又は出資金の総額)
- 取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託)
運送業の場合、下請取引は役務提供委託に該当する点にご注意ください。
また、資本金でみた対象となる取引は下記のとおりです。
- 資本金が3億1円以上の企業が資本金3億円以下の会社や個人事業者に委託した場合
- 資本金が1千万1円以上~3億円以下の企業が資本金1千万円以下の会社や個人事業者に委託した場合
資本金と取引内容、どちらかに該当していれば、下請法の対象となります。
運送業で対象となる役務提供委託とは
運送業で下請法の対象となる役務提供委託とは、元請け企業が、請け負った役務を下請け企業に再委託することです。
例えば、荷主から貨物運送の委託を受けた元請け企業が、請け負った役務(サービス)の全部又は一部を下請け企業へ再委託した場合に、役務提供委託の対象となります。
ただし、荷主から請け負った作業貨物運送にのみ対象となる点に注意が必要です。
例えば、荷主から請け負った貨物運送とは別で、梱包作業が必要な場合、それを下請け企業に委託したときは、役務提供委託対象にはなりません。
【2024年】下請法の改正ポイント
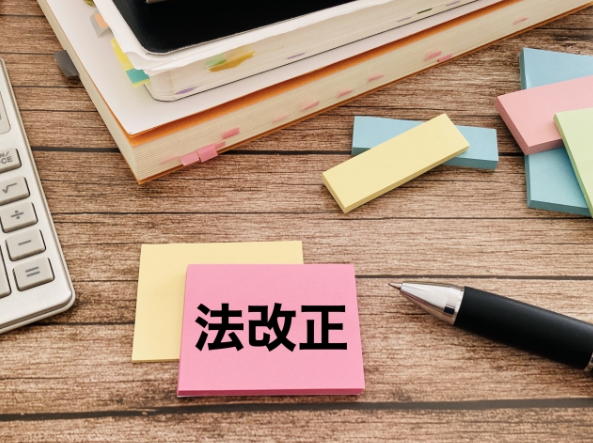
公正取引委員会は、2024年に下請法の運用基準を改正し、運用ルールも変更しています。
また、今回の法改正によって、下請法の対象となる対象事業者に対して、妥当な対価を支払うような処置が施されたのがポイントです。
主に改正された内容は下記のとおりです。
- 手形サイトが60日を超える場合は「割引困難な手形」として行政指導の対象
- 「買いたたき」の解釈を明確化した
下請代金に手形を使用する場合、手形サイトが60日を超える手形等は「割引困難な手形」として行政指導の対象となりました。
また「買いたたき」の解釈を具体的に改正しています。
改正された運用基準では「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」として新たに追加された項目は下記のとおりです。
- 従前の給付に係る単価で計算された対価に比して、著しく低い下請代金の額
- 労務費や原材料価格などのコスト上昇が公表資料から把握できる場合において、据え置かれた下請代金の額
今回の改正で、下請け企業が価格交渉しやすくなったといえるでしょう。
下請法の改正に伴う注意点
今回の下請法の改正で、元請け企業が注意すべき点は下記のとおりです。
- 手形サイトが60日を超えない手形とする
- 買いたたき行為とみなされる「通常支払われる対価に比して著しく低い代金」に該当した取引をしていないこと
上記について、今一度、自社や取引先との内容を見直すことをおすすめします。
下請法の改正によって発生する義務

下請法の改正によって、元請け企業は下請け企業との取引において、下記の内容が義務付けられます。
- 発注した物品等を受領した日から起算して60日以内で下請代金の支払期日を定める
- 支払期日までに支払いしなかった場合、遅延利息(年率14.6%)の支払い義務が発生する
- 発注内容を明確に記載した書面を交付する
- 取引に関する記録を書類として作成して2年間保存する
公正取引委員会及び中小企業庁では、毎年、書面調査を実施しています。
公正な下請取引が行われているかを把握するために調査を行っているのです。
また、下請法に違反した企業に対して、違反行為の中止を求め、減額や遅延利息の支払い等を指導します。
さらに、再発防止の措置を実施するよう勧告・公表も行っているので、十分に注意しましょう。
下請法の取締り対象になる事例
この章では、下請法の取締り対象になる下記の事例をご紹介します。
- 買いたたき事例
- 元請け企業の禁止行為事例
買いたたきや禁止行為には、さまざまな事例があるため、詳しく見ていきましょう。
買いたたき事例
買いたたきの事例として下記の内容を参考にしてください。
|
買いたたき事例 |
内容 |
|
下請代金の据え置き |
親事業者から下請事業者に対して、使用することを指定した原材料の価格が高騰していることが明らかな状況において、下請事業者から、従来の単価のままでは対応できないとして単価の引き上げを求めたにもかかわらず、親事業者は、下請事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置いた。 |
|
納品後の下請代金の決定 |
親事業者は、下請代金の額を定めずに部品を発注し、納品された後に下請事業者と協議することなく、通常の対価相当と認められる下請事業者の見積価格を大幅に下回る単価で下請代金の額を定めた。 |
|
短納期発注 |
親事業者は、下請事業者との間で単価等の取引条件については年間取決めを行っているが、緊急に短い納期で発注する場合は別途単価を決めることとしていた。親事業者は、週末に発注し週明け納入を指示した。下請事業者は、深夜勤務、休日出勤により納期に間に合わせ、当該加工費用は人件費が相当部分を占めることから年間取決め単価に深夜・休日勤務相当額を上乗せした下請単価で見積書を提出した。しかし、親事業者は、下請事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、通常の対価相当と認められる下請事業者の見積価格を大幅に下回る年間取決め単価で下請代金の額を定めた。 |
|
多量発注を前提した価格で少量の発注 |
親事業者は、単価の決定に当たって、下請事業者に1個、5個及び10個製作する場合の見積書を提出させた上、10個製作する場合の単価(この単価は1個製作する場合の通常の対価を大幅に下回るものであった。)で1個発注した。 |
|
理由のない差別的な代金の決定 |
親事業者は、自社の目標額を達成するためにはコストダウンする必要があるとして、一部の下請事業者が納入する部品について他の下請事業者が納入する同一の部品よりも著しく低い単価を定めた。 |
|
協議のない代金の一定比率の引き下げ |
親事業者は、国際競争力を強化するためにはコストダウンをする必要があるとして主要な部品について一律に一定率引き下げた額を下請単価と定めたため、対象部品の一部の単価は通常の対価を大幅に下回るものとなった。 |
|
特定の地域又は顧客向けであることを理由にした低価格での決定 |
親事業者は、海外では国内よりも安い販売価格でないと売上が伸びないことを理由に、海外向けの 製品に用いる部品について国内向けの製品に用いる同一の部品よりも著しく低い単価を定めた。 |
元請け企業の禁止行為事例
元請け企業の禁止行為の事例は下記を参考にしてください。
|
禁止行為の事例 |
内容 |
|
下請代金の支払遅延 |
下請代金の支払いについて「毎月20日納品締切、締切後40日現金支払」の支払制度を採っていたため、下請事業者から物品等を受け取ってから60日を超えて下請代金を支払っていた。 |
|
受領拒否 |
発注元の都合による仕様等の変更を理由として、下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定められた納期に下請事業者の給付を受領しなかった。 |
|
不当返品 |
受入検査を下請事業者に文書で委任していないにもかかわらず、受領後に不良品を返品した。 |
|
物の購入強制・役務の利用強制 |
外注担当者が下請事業者に対して、自社が取り扱う商品の購入等を要請した。 |
|
有償支給原材料等の対価の早期決済 |
下請事業者が製造加工して納品するまでの期間を考慮せずに、有償支給した原材料の代金を下請代金から控除していた。 |
|
割引困難な手形の交付 |
手形期間が130日の手形を交付した。 |
|
不当な経済上の利益の提供要請 |
委託取引先の登録制を採っているが、登録された下請事業者に対し、「協定料」と称して現金の提供を要請した。 |
|
不当な給付内容の変更・やり直し |
親事業者や発注元の都合を理由に、下請事業者に責任がないのに発注内容を変更し、変更に伴う必要な費用の一部を下請事業者に負担させていた。 |
|
報復措置 |
禁止行為に該当する行為を親事業者が行った場合に、下請事業者がその事実を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引数量を削減した。 |
運送業の下請法に関わる気になる質問
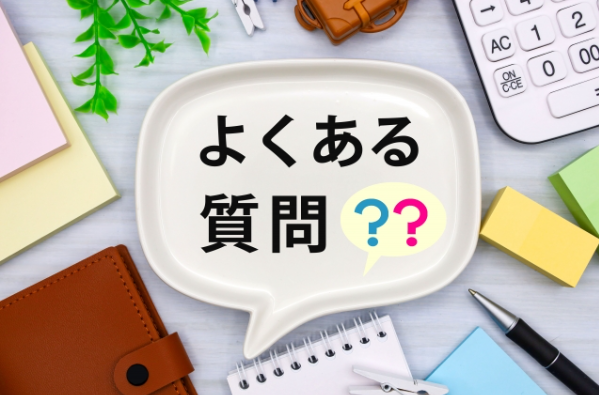
この章では、下請法に関わる気になる質問を2つ厳選してご紹介します。
- 物流特殊指定と下請法の違いは?
- 下請法は輸送作業のみでも対象ですか?
それぞれの質問を詳しく見ていきましょう。
物流特殊指定と下請法の違いは?
「物流特殊指定」は、独占禁止法上の告示であり、下請法とは異なります。
物流特殊指定と下請法は、下記の関係によって対象が異なる点に注意しましょう。
- 荷主から物流事業者(元請け)が運送・保管の委託を受けた場合は「物流特殊指定」が対象
- 物流事業者(元請け)から物流事業者(下請け)が運送・保管の再委託を受けた場合は「下請法」が対象
物流業界では、荷主の地位が事業者に優越していることが多く、優越的地位の濫用が特に問題になりがちです。
そのため、公取委が特に定めたルール(物流特殊指定)が告示されていることを理解しておきましょう。
下請法は輸送作業のみでも対象ですか?
元請け企業が、荷主から委託された内容に輸送作業があり、再委託された場合は対象となります。
ただし、下請法の対象となる取引には、元請けと下請け企業の資本金も関係するため確認しておきましょう。
運送業の下請法は改正によって改善され始めている

下請法は、下請け企業の保護を目的とした法律であり、元請け企業と下請け企業が公正な取引を行うために施行されました。
2024年には、さらに具体的に改善された法改正が行われており、今回の改正で、下請け企業が価格交渉しやすくなったといえるでしょう。
自社の取引内容が、下請法の対象となっているのか、買いたたきや禁止行為に該当していないかも確認しておくと安心です。
下請け業務でドライバー不足にお悩みなら、全国に対応している求人・転職サービスの「ドラピタ」に掲載がおすすめです。
「ドラピタ」では、ドライバー案件に特化した職種軸で検索が可能なため、貴社の狙ったターゲットへ求人原稿を訴求できます。
掲載について詳しく知りたい方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。