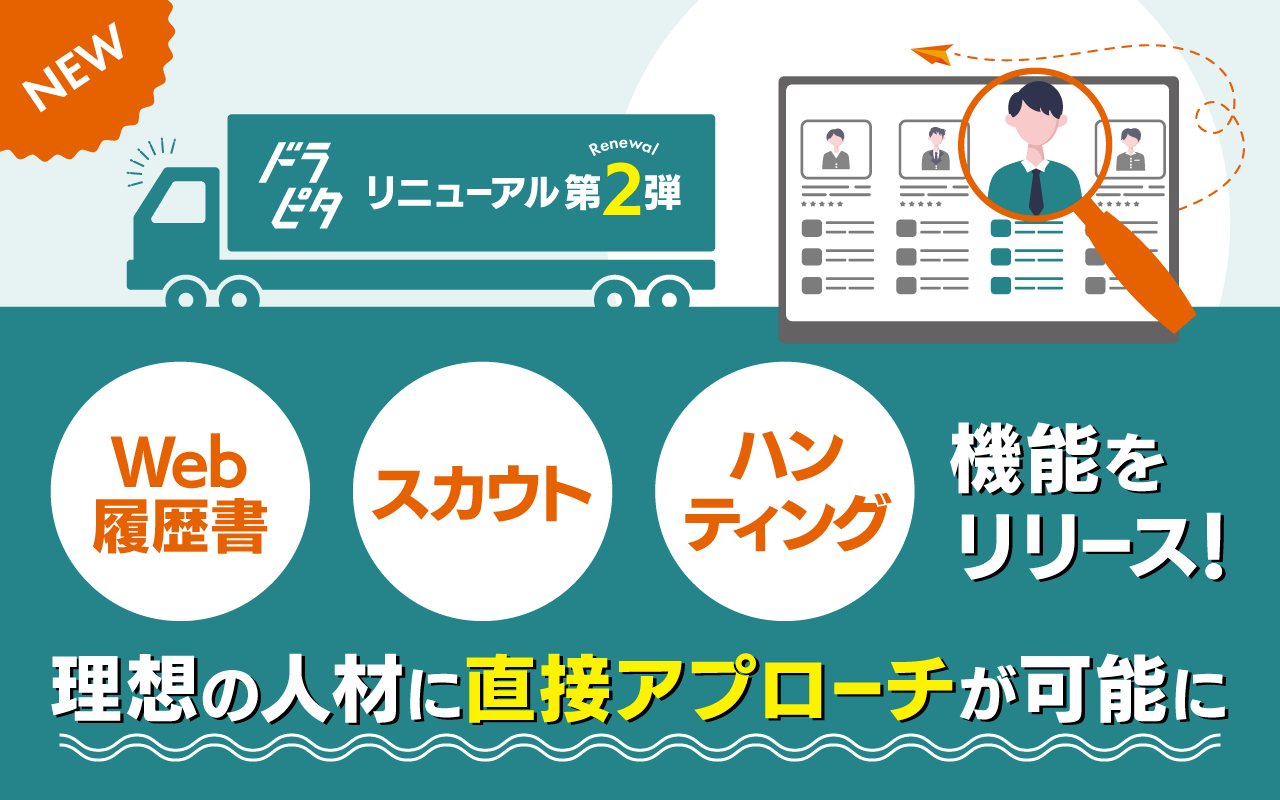荷主の安全配慮義務は、運送業者やトラックドライバーが安心して業務を行うための重要な義務です。
とはいえ、具体的にどのような配慮が必要なのか分からない荷主もいるでしょう。
法改正の経緯や安全配慮義務が新設された背景、違反時のペナルティなどを把握しておけば、安全運行と信頼獲得に大きく貢献します。
この記事では、荷主が果たすべき安全配慮義務のポイントと注意点を解説します。
荷主の安全配慮義務とは?

2018年に改正された貨物自動車運送事業法が施行され、安全配慮義務が新たに荷主に課されました。
荷主の安全配慮義務は、トラックドライバーの働き方改革を推進するうえで欠かせない取り組みで、法令違反や事故リスクを回避する責任を荷主に負わせるものです。
具体的には、合理的な到着時間や配送計画の策定、荷待ち時間の削減、過積載や急な計画変更の回避など、トラックドライバーが安全かつ健康的に業務を行える条件を整える必要があります。
長時間労働や過密スケジュールで疲弊するトラックドライバーが増えている物流業界の現状を改善するには、荷主による積極的な安全配慮が欠かせません。
また近年はトラックドライバーの人手不足が深刻化し、1人あたりの業務負荷の高さから転職者が減っています。
そこで、事故リスクの低減や労働環境の改善を目指すうえで、荷主が安全運行を阻害しないよう配慮すれば、人材確保や企業イメージの向上につながります。
今後も法改正や社会情勢の変化に合わせ、荷主が主体的にルールを見直し、運送事業者との連携を強化する必要があります。
荷主の安全配慮義務が新設された背景

荷主の安全配慮義務が新設された背景には、以下のような理由があります。
- トラックドライバーの高齢化と減少が問題になっているため
- トラックドライバーの安全と福祉を守るため
- 荷待ち時間が増加しているため
トラックドライバーの労働環境が厳しくなっているなか、雇用の流出を止めるために安全配慮義務が新設されました。
トラックドライバーの高齢化と減少が問題になっているため
物流業界は、トラックドライバーの高齢化と減少が深刻です。
国土交通省のデータによると、平成7年時点で98万人いたドライバーは、平成27年には76万人まで減りました。
参照:国土交通省|物流生産性向上に資する幹線輸送の効率化方策の手引き
ECサイトの普及により物流量は増加しているため、需給と供給の不均衡が際立っています。
さらに、高齢化率も大きな問題です。
平成30年の労働力調査では、45歳以上の労働者割合が全産業平均32.8%に対し、道路貨物運送業は44.8%と高い数字が示されました。
参照:国土交通省|「ホワイト物流」推進運動の建設資材分野における進め方について
運送量が増える一方で、長時間労働や免許制度の変更などが要因となり、若い世代の参入が年々減っています。
ドラックドライバーの高齢化が進むと将来的な担い手が不足し、輸送の安定確保が難しくなるおそれがあります。
実際、近年の国土交通省は若年層へのアピール強化や職場環境の改善に積極的です。
安全配慮義務の新設は、こうした運送業界の構造的な問題を解消し、将来的な物流の安定を促進します。
トラックドライバーの安全と福祉を守るため
荷主に課された安全配慮義務は、トラックドライバーの安全と福祉を守る目的で導入されました。
過度な到着時間の設定や過積載指示などは事故リスクを高め、業界の魅力低下や人手不足を深刻化させます。
荷主には貨物の安全性を最優先に扱う責任があり、適切な包装や取扱指示、安全情報の共有を行う必要があります。
荷主と運送事業者が連携して、トラックドライバーの安全と福祉を守る姿勢が重要です。
荷主からの安全配慮があれば、トラックドライバーの労働環境が改善し、物流全体の安全性と効率性も向上します。
また、トラックドライバーの定着率向上にもつながり、慢性的な人手不足の改善にもつながります。
荷待ち時間が増加しているため
近年は消費者ニーズが複雑化し、迅速かつ多様な運送が求められるようになりました。
これにともなって、トラックドライバーの荷待ち時間が増え、拘束時間も長くなっています。
平成27年の「トラック輸送状況の実態調査」では、荷待ち時間がない運行の平均拘束時間は11時間34分、荷待ち時間がある運行は13時間27分となり、約2時間の差が生じました。
参照:国土交通省|トラック輸送状況の実態調査結果(全体版)
こうした長時間拘束が常態化するとトラックドライバーに疲労が蓄積しやすく、安全運転に支障をきたすおそれがあります。
過剰な待ち時間によるストレスが交通事故のリスクを高めることは多くのデータで示唆されており、安全配慮義務にはこうした状況を改善する目的があります。
荷主の安全配慮義務の具体例

荷主となる企業が具体的に配慮すべき項目は、以下の通りです。
- 合理的な配送時間の設定
- 荷待ち時間の減少
- 貨物や配送計画の急な変更防止
- 万が一のペナルティ設定
義務違反にならないように、それぞれの項目を解説します。
合理的な配送時間の設定
荷主が安全配慮義務を果たすには、到着時間を合理的に設定する必要があります。
短すぎる時間を指定すると、トラックドライバーが安全運転や休息を確保できなくなり、事故リスクが高まります。
さらに、交通渋滞や悪天候など突発的なトラブルが発生した場合、厳しい時間指定を守るために無理な運転を強いられる可能性があり危険です。
こうした問題を防ぐためには、実際の交通事情や積み込み作業に要する時間を十分に考慮した余裕あるスケジュールを組む必要があります。
トラックドライバーに負担をかける配車計画は、結果的に品質低下や交通トラブルなど悪影響を招きかねません。
加えて、合理的な時間設定はトラックドライバーのモチベーション向上にも役立ち、人材確保にもつながるなど、長期的なメリットもあります。
安全配慮義務は法律上の責任だけではなく、物流効率や企業の信頼にも直結する重要な要素です。
荷待ち時間の減少
荷待ち時間の削減は、トラックドライバーの負担を軽減するうえで欠かせません。
倉庫の混雑や手続きの遅れで生じる待機は、トラックドライバーの労働時間をむやみに延ばし、安全運行の妨げになります。
長時間の待機時間は、ドライバーの心身の疲労が増し、運転中の集中力が低下しやすくなるため事故リスクも高まります。
荷主としては、事前の打ち合わせや受け入れ態勢の整備を進め、待機が最小限になるよう努める姿勢が必要です。
具体的な方法としては、倉庫側での検品・仕分け作業を効率化し、到着予定時刻に合わせてスタッフを配置するなどが考えられます。
さらに、書類手続きのオンライン化や、予約システムを導入すれば、到着から積み込みまでの時間短縮が可能です。
荷待ち時間の削減はドライバーの労働環境を改善するだけでなく、企業にとってもコスト削減や顧客満足度向上を期待できます。
貨物や配送計画の急な変更防止
貨物や配送計画を直前で変更すると、ドライバーの安全運行に大きな負担が生じます。
安全配慮義務を守るうえでも、急な配送計画変更は避けましょう。
例えば、積み込み直前に貨物量を増やすと、運送業者が想定していた車両では法定積載量を超える可能性があります。
そうなるとトラックドライバーは過積載状態での運行を強いられ、重大事故につながるリスクが高まります。
こうしたトラブルを避けるためにも、荷主は早めに運送事業者と情報を共有し、余裕を持った配送スケジュールを立案しましょう。
余裕をもって貨物量や配送先を確定すれば、必要な人員や車両の手配が円滑に進み、結果としてコスト削減やスムーズな業務運営を実現しやすくなります。
急な変更が常態化すると、運送業者から敬遠されるリスクも高まるため、長期的な取引関係を築くうえでも安定した配送計画が必要です。
万が一のペナルティ設定
運送は天候や交通事故、道路工事など、トラックドライバーの努力では回避しきれない事象が起こります。
万が一の事態で遅延が発生する場合、トラックドライバーはスケジュール調整が難しくなります。
荷主が遅延に対して過度なペナルティを科すと、安全運転よりも納期遵守を最優先せざるを得なくなり、事故リスクが増大しかねません。
一例を挙げると、遅れに対して高額な罰金や厳格な違約金などです。
安全配慮義務を果たすには、遅延発生時の状況を正しく把握し、やむを得ない事情があるときは柔軟に対応する姿勢が求められます。
運送業者と定期的に連絡を取り合い、渋滞情報や天候の変化を共有すれば、大幅な遅延を防ぐ工夫もできます。
荷主が無理なスピード違反や過積載などが起こりにくい環境を整えることは、企業の社会的信用を高めるうえでも大切です。
安全配慮義務違反時のペナルティ

荷主が安全配慮義務を守っていない疑いがある場合、企業名が公表される流れは次のとおりです。
- 国土交通大臣と関係行政機関が、問題のある可能性を把握した荷主情報を共有
- 国土交通大臣が関係行政機関と連携し、荷主へ働きかけを実施
- 国土交通大臣が関係行政機関と連携し、荷主へ要請を行う
- 国土交通大臣が関係行政機関と連携して勧告を行い、企業名を公表
「働きかけ」は自主的な改善を促す呼びかけで、「要請」はより踏み込んだ行政指導です。
働きかけや要請の段階で状況が是正されれば、それ以上の措置はとられません。
しかし、従わなかった場合、さらに強い勧告や企業名公表へと進みます。
また、荷主の行為が独占禁止法違反にあたる可能性がある場合、公正取引委員会へ通知されるケースもあります。
行政指導が入る前に適切な対策を講じて、企業イメージを守りつつ安全配慮義務を実践しましょう。
参照:国土交通省|トラック運送事業に係る各種施策について
荷主が取るべき安全配慮義務の対応策

荷主が取るべき安全配慮義務の対応策は、以下の2つです。
- マニュアルの整備と従業員教育
- ハラスメント対策の実施
従業員一人ひとりが正しく安全配慮義務を実施できるような環境を構築しましょう。
マニュアルの整備と従業員教育
マニュアル整備は、安全配慮義務を遂行するうえで重要な基盤です。
運送や荷役の現場では、小さなミスが重大事故につながりかねません。
統一された基準や手順をマニュアル化すれば、従業員が迷わず作業を進められます。
マニュアル導入時には、現場の実態やリスクを踏まえた内容を盛り込み、トラックドライバーだけでなく荷役スタッフや管理部門も共通認識を持つことが大切です。
マニュアルを作成して終わりではなく、定期的に見直しを行い、運用の改善を図りましょう。
ハラスメント対策の実施
ハラスメントは職場環境を悪化させる大きな要因で、安全配慮義務とも深く関係します。
業務命令の範囲を超えた叱責や人格否定、セクハラ・パワハラなどが横行すると、従業員のメンタルヘルスが損なわれ、労働意欲の低下や離職を招きやすくなります。
特に2022年4月に改正された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、中小企業にも適用範囲が拡大し、パワーハラスメント防止措置が義務化されました。
具体的には、ハラスメントに関する研修やマニュアル整備、社内ルールの周知徹底が挙げられます。
ハラスメント対策を徹底すれば、従業員同士やトラックドライバーとのコミュニケーションが円滑になり、生産性も向上しやすくなります。
トラックドライバーの精神状態が不安定になると、集中力が散漫になり重大事故のリスクが増すため、運送事業者内でハラスメントが放置されていないか目を配り、必要な改善を促しましょう。
荷主が安全配慮義務を徹底してドライバーが働きやすい環境を作ろう

荷主の安全配慮義務は法令遵守だけでなく、トラックドライバーの労働環境や物流効率、企業イメージにも大きく影響します。
過度なスケジュールや不合理な荷待ち時間は、トラックドライバーに負担をかけるだけでなく、事故リスクの増大や離職率の上昇を招きかねません。
逆に、余裕ある配送計画や適切なハラスメント対策を行えば、労働条件が改善し、業界全体の魅力向上にもつながります。
トラックドライバー不足が深刻化する昨今だからこそ、荷主と運送事業者が互いに協力し合う関係を築く必要があります。
トラックドライバー不足で困っている企業は、物流業界に特化した求人サイト「ドラピタ」を活用してみましょう。
優秀な人材を確保しつつ、安全で働きやすい環境を整えるためにも、荷主側の配慮が欠かせません。
企業の信頼と社会的評価を高めるためにも、今こそ安全配慮義務を実践していきましょう。